

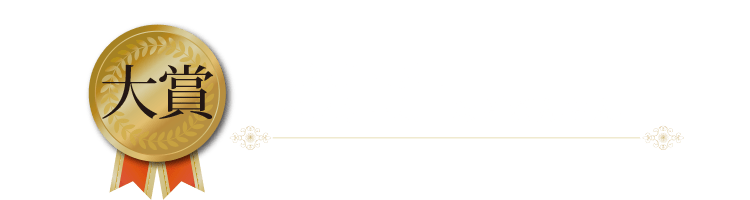

高校を卒業後、就職した。全寮制の会社だった。
たくさんの同期に恵まれたけれど、ふるさとから離れて暮らすことは18才の私にはまだ寂しく、いつも帰りたいと布団の中で泣いていた。
仕事は想像を絶するほど厳しく、毎日怒鳴られ、50人ほどいた同期もあっという間にほとんどふるさとに帰っていった。
つらい日々、仕事を終えて寮に帰るといつも「おかえり、おつかれさん」と寮母さんが出迎えてくれ、泣いているわたしを部屋に招き入れてくれて話を聞いてくれ、そして生まれて初めて豆を引いたコーヒーを飲ませてくれた。
苦い、と思ったし美味しいとは思えなかったが香りがめっぽう良かった。それは幼いわたしにもわかった。
寮母さんのことはみんな親しみを込めて「おばちゃん」と呼んでおり、たぶん50代前半、おしゃれ、本棚には純文学がぎっしり、小さなキッチンには名前はわからないが美しいコーヒーを入れる道具がならんでいて、テレビの上には昨年虹の橋を渡ったと言う愛犬の写真が飾られていた。そして1人で暮らしていた。
わたしは自分の家が裕福でないこと、父が蒸発してしまって母が1人で必死に子育てと、父の両親の面倒を見ていること、そしてこの会社をやめたいけれど、それは母の負担になりわずかな仕送りもできなくなることなどをおばちゃんに聞いてもらっていた。
初めてのお正月、同期で1人だけ仕事だった。
疲れて寮に帰っておばちゃんに手渡されたものは小さな三段の重箱。それは1人用のおせちだった。口どりから全て手作りの美しいお節料理。
「お母さんのおせち食べたかったよね?よく頑張ったね、お母さんのおせちには敵わないけど食べてね」と言われ寮の部屋で1人おばちゃんのお節をいただいた。
つやつやの黒豆は母の得意料理、涙がぽろぽろこぼれて…ほんのりあまくて、せつなくて、悲しくて、幸せで、人生で一度きりしか味わったことのない特別なわたしだけのお節だった。


「重箱の涙」
昨年、警察官を定年退職したが、三十年以上の昔、忘れられないおせち料理の話がある。
刑事だった私が年の瀬に逮捕したのは二十歳の被疑者Nだった。
粗暴犯で相手に大きな傷害を負わせた。Nは若いがすでに多くの前科前歴があり、取調室でも不敵な薄笑いを浮かべるだけで雑談には応じるが犯した罪は認めない。
この手の被疑者には根気よく付き合って自供の隙を狙うしかないのだが、Nの拘留期間は年を越すことが予想されていた。
明日が大晦日という日。私とNは朝から取調室で対峙していたがそのうちに昼休みになった。
現在では被疑者の昼食は必ず留置場に戻って摂る決まりだが、当時は取調室に官弁という粗食の弁当を持ち込んで摂らせていて、逃走防止の観点から取り調べる刑事と一緒に食べていた。
Nはプラスチックの箱に入った白米と佃煮、揚げ物が一個だけの弁当を黙って咀嚼する。
その前で私は共働きの妻が作った弁当を広げた。
そういえば、少し早いけどおせち料理を作ったからと、今日は小さな重箱だ。
Nは下を向いて箸を口に運んでいる。
少し迷って私はおせちの幾つかを重箱の蓋に載せてNに押しやった。
昆布巻き、蒲鉾、お煮染め、八幡巻き。
箸を止めたNは驚いて私を見た。
「数の子とか高いのはないで。我慢しろ。」
「え?いいんですか?」
「いいよ。口に合うか?」
頭を下げたNは全てを平らげたがやがて箸が震え、重箱の蓋に涙が伝った。
知っていた。Nは離婚した両親に見放されて施設で育った。
「いいですね…手作りのおせち。」といったNが両手を膝の上に置いて居住まいを正す。
これは自供するサインだ。
「N君も。手作りのおせち、作ってくれる好い人えを早くみつけや。」そしてNは罪を認めた。
三十年以上前の規則がない時代に私がしたことは今なら便宜供与で処分ものだ。
だが、あれは頑なだったNが重箱の蓋に落とした涙と一緒に、手作りのおせち料理の味が落とした取り調べだったのだと今でも信じている。


あれは私が24歳の時のクリスマスイブだった。
事の発端は夫の一言から始まった。
婚約中だった夫は秋に徳島から東京に転勤し、お正月は私が夫のところへ出向くことになっていた。
その日、電話で取り留めのない話をしていると、夫が突然、「君の手作りのおせちが食べたいなあ。僕、ごまめと栗きんとんが好きなんよ」と、言い出した。
私は一瞬ドキッとしたが、「私も大好き。作って持って行くわ」と、話を合わせた。
電話を切ってから、私は心の中で呟いた。
──ごまめって、どんな豆?
栗きんとんって、何なん?──。
私は夫と付き合い始めた頃に特技を聞かれて、その場しのぎで「料理」と答えた。
そして得意料理は何かと問われ、思い付きで、「おせち」と口走ってしまったのだ。
私は電話の一部始終を母に報告すると、母は目が点になった。
「カレーしか作ったことがないあんたにそんな難しいもん、出来るはずがないやろ」
私は母に非難囂囂を浴びせられた。
それから大晦日まで、私は毎日買い出しに付き合わされ、家では一日中台所に監禁された。
「あんたはほんまにお調子者なんやから。尻拭いせなあかん親の身にも、なってみな!」
母の小言が飛び交う中で、私は、母のサツマイモを裏ごししている姿を眺めながら、おせちって、すごく手間のかかるものだということを実感した。
と同時に店頭で売られているプロの作ったものがどうしてあんなに高価なのかも腑に落ちた。
そしていよいよ元旦が来た。私は三段重を抱え東京に向かった。
重箱の蓋を開けた瞬間、夫は感嘆の声を上げた。
結婚して41年の歳月が経ったけれど、私は今でもあの時の夫の表情が目に浮かんでくる。
私のおせち神話は、日々の私の料理から早々に夫にバレた。
母が高齢になりおせちが作れなくなってからは、毎年お取り寄せをするようになった。
今年の元旦、夫は豪華なおせちを見て、苦笑いしながら言った。
「君の一番の得意技はなあ、『大嘘がつけること』だよ」

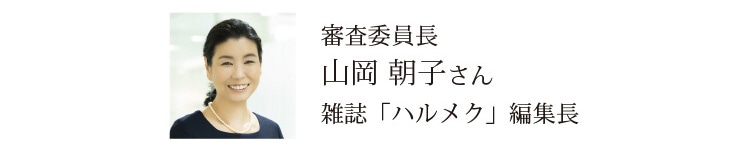
年末のほろ苦い出来事、年始の晴れやかな場面、そして家族や友人とのエピソードなど、さまざまな切り口の思い出話がたくさん集まりました。
「おせちって誰にとっても特別な存在なのだな」とあらためて感じる審査となりました。中でも受賞の3作品は当時の時代背景を含めて登場人物が生き生きと描かれ、まるで短編小説のような趣。
ぜひ皆様にも、美味しいおせちと同様、このエッセイを味わっていただきたいと思います。
「おせちって誰にとっても特別な存在なのだな」とあらためて感じる審査となりました。中でも受賞の3作品は当時の時代背景を含めて登場人物が生き生きと描かれ、まるで短編小説のような趣。
ぜひ皆様にも、美味しいおせちと同様、このエッセイを味わっていただきたいと思います。
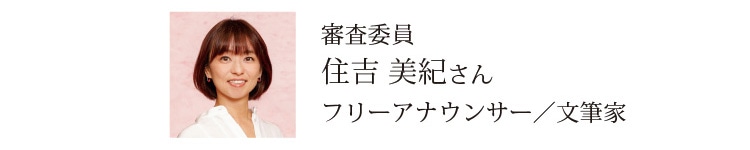
改めて、おせちが、いかに家族の大切な思い出と結びついているものであるかを実感しました。
寄せられた思い出話はそれぞれが、おせちによって紡がれた、親子、夫婦、おじいちゃんおばあちゃんと孫の間の「絆」の物語でした。
さらに、おせちは、家族でなくても、まるで家族のような濃度で人と人の気持ちをつないでくれる特別なものなのだということも発見しました。
寄せられた作品を読みながら、何度も涙。審査は難儀でした。そしてお正月におせちを囲むのが楽しみになりました!
寄せられた思い出話はそれぞれが、おせちによって紡がれた、親子、夫婦、おじいちゃんおばあちゃんと孫の間の「絆」の物語でした。
さらに、おせちは、家族でなくても、まるで家族のような濃度で人と人の気持ちをつないでくれる特別なものなのだということも発見しました。
寄せられた作品を読みながら、何度も涙。審査は難儀でした。そしてお正月におせちを囲むのが楽しみになりました!
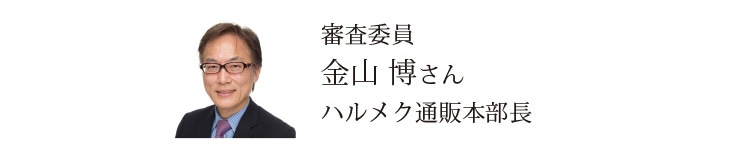
たくさんの思い出話を有難うございました。
会社のデスクで読ませていただいたのですが、周りを気にしながら、泣いたり、笑ったり。ひとつひとつ、大切な思い出の中をご一緒させていただきました。
能登で被災された方々のことも想い浮かべながら、改めて、おせちはご家族の絆であると感じました。
今年ももうすぐおせちの季節。私も、家族と大切なときを過ごそうと思います。
こんな気持ちに誘ってくださった皆様に感謝します。
会社のデスクで読ませていただいたのですが、周りを気にしながら、泣いたり、笑ったり。ひとつひとつ、大切な思い出の中をご一緒させていただきました。
能登で被災された方々のことも想い浮かべながら、改めて、おせちはご家族の絆であると感じました。
今年ももうすぐおせちの季節。私も、家族と大切なときを過ごそうと思います。
こんな気持ちに誘ってくださった皆様に感謝します。

\ ノミネート作品は25作品 /
「おせちとわたし」 ノミネート作品01
子供のころからおせちの中の「栗きんとん」と「黒豆」が大好物だった私。
小学校4年生か5年生のお正月、私はこの大好物を独り占めしたいと考えた。
我が家のおせちは、品数がさほど多くない。
実際、栗きんとんと黒豆にしか興味がなかった私の記憶は多少あいまいだが、はっきりと覚えているのは筑前煮、伊達巻、昆布巻き、カズノコ、田作り、かまぼこ、なます、栗きんとん、黒豆、白豆といったレパートリー。
多くない食材を重箱に詰め元旦から食べる。
食べて減った分を冷蔵庫に保管しているタッパーから足してまた翌朝満杯の重箱が食卓へ並ぶのだ。
どこにたくさん入っていて、どこから食べれば自分だけがお腹いっぱい好きなものを食べられるかは、当然小学生の私だって理解できている。
「好きなものを独り占めしたい欲に駆られた小学生の私」には、この繰り返しがルールなんだと大人しく見ていられるはずなどなかった。
小学4年生か5年生の私は、その年の元旦、みんなでおせちを食べている最中、食事を早々に切り上げ、栗きんとんと黒豆のタッパーだけを冷蔵庫から持ち出し、自分の部屋でこっそり食べた。
カレースプーンで最初は半分すくいひと口、幸せが口一杯に広がった。
二口目はもう少し多くすくい、三口、四口…それはもう止まらない。
気づけば、栗きんとんも黒豆もタッパーは空っぽ。
程なくして、冷蔵庫にふたつのタッパーがないことに気づかれ、元日早々ゲンコツ落とされた。
あれから45年ほどが過ぎ、4児の母として自分でおせちの準備をする立場。
相変わらず栗きんとんと黒豆が大好きな私は、どうしてもこの二つだけは大量に準備してしまうが、我が家でこのふたつに箸を伸ばすのは私だけ。
今では望まずともお腹いっぱい独り占めの状態が嬉しくもあり、少し寂しい。
小学校4年生か5年生のお正月、私はこの大好物を独り占めしたいと考えた。
我が家のおせちは、品数がさほど多くない。
実際、栗きんとんと黒豆にしか興味がなかった私の記憶は多少あいまいだが、はっきりと覚えているのは筑前煮、伊達巻、昆布巻き、カズノコ、田作り、かまぼこ、なます、栗きんとん、黒豆、白豆といったレパートリー。
多くない食材を重箱に詰め元旦から食べる。
食べて減った分を冷蔵庫に保管しているタッパーから足してまた翌朝満杯の重箱が食卓へ並ぶのだ。
どこにたくさん入っていて、どこから食べれば自分だけがお腹いっぱい好きなものを食べられるかは、当然小学生の私だって理解できている。
「好きなものを独り占めしたい欲に駆られた小学生の私」には、この繰り返しがルールなんだと大人しく見ていられるはずなどなかった。
小学4年生か5年生の私は、その年の元旦、みんなでおせちを食べている最中、食事を早々に切り上げ、栗きんとんと黒豆のタッパーだけを冷蔵庫から持ち出し、自分の部屋でこっそり食べた。
カレースプーンで最初は半分すくいひと口、幸せが口一杯に広がった。
二口目はもう少し多くすくい、三口、四口…それはもう止まらない。
気づけば、栗きんとんも黒豆もタッパーは空っぽ。
程なくして、冷蔵庫にふたつのタッパーがないことに気づかれ、元日早々ゲンコツ落とされた。
あれから45年ほどが過ぎ、4児の母として自分でおせちの準備をする立場。
相変わらず栗きんとんと黒豆が大好きな私は、どうしてもこの二つだけは大量に準備してしまうが、我が家でこのふたつに箸を伸ばすのは私だけ。
今では望まずともお腹いっぱい独り占めの状態が嬉しくもあり、少し寂しい。
「おせちとわたし」 ノミネート作品02
「1月1日までは、がんばってね。」 末期がんの母に、ずっとお願いしていました。
食べ物の好みが変わり、嚥下力も低下し、だんだんと食べられるものが少なくなる日々。
食べられないかもしれないという気持ちを脇に置いて、年末に食材をそろえ、おせち料理を一品一品、丁寧に作っていきました。
味の濃いものを好むようになっていたので、いつもより、調味料を多く。また、柔らかく仕上がるように心掛けた結果、今までで一番の仕上がりになりました。
何か食べられるものはあるかな…とドキドキ。
元旦の朝は全部を少しずつカットして、お重に並べました。
なかでも、栗きんとん、昆布巻、数の子がおいしかったようで、3が日の間、ずっとたべてくれました。
亡くなる2週間前にあれだけ食べられれば、大往生。
おせち料理の後は、プリンのような流動食しか食べられなくなったので、最後に食べた食事はおせち料理と言えるでしょう。
最後までおいしいものが食べられるようにというのが、娘と私の願いでした。
私たちの思いが伝わり、最後まで手作りの料理を食べてくれた母に感謝です。
食べ物の好みが変わり、嚥下力も低下し、だんだんと食べられるものが少なくなる日々。
食べられないかもしれないという気持ちを脇に置いて、年末に食材をそろえ、おせち料理を一品一品、丁寧に作っていきました。
味の濃いものを好むようになっていたので、いつもより、調味料を多く。また、柔らかく仕上がるように心掛けた結果、今までで一番の仕上がりになりました。
何か食べられるものはあるかな…とドキドキ。
元旦の朝は全部を少しずつカットして、お重に並べました。
なかでも、栗きんとん、昆布巻、数の子がおいしかったようで、3が日の間、ずっとたべてくれました。
亡くなる2週間前にあれだけ食べられれば、大往生。
おせち料理の後は、プリンのような流動食しか食べられなくなったので、最後に食べた食事はおせち料理と言えるでしょう。
最後までおいしいものが食べられるようにというのが、娘と私の願いでした。
私たちの思いが伝わり、最後まで手作りの料理を食べてくれた母に感謝です。
「おせちとわたし」 ノミネート作品03
我が家には娘、息子、娘と3人子供がいますが、そのうち娘2人のパートナーはそれぞれ国は違いますが外国人です。
そのパートナーに日本のおせち料理を紹介するのが、毎回大変というか、とても面白いのです。
長女は彼に対して、料理一つ一つ丁寧に(子孫繁栄の子持ち昆布、出世魚の鰤の照り焼きなど)説明をします。
それに対して、次女のそれは超適当で、きんとんを不思議そうに見た彼に対して「That’s so sweet」
数の子には「That’s a big fish egg 」というあり様。
それを見てみんな大笑い。
甘いとか卵とかいう説明でなく、もっと他にあるでしょ!と流石の私たち家族も思い、みんなで必死の説明、お正月から英会話教室状態になりました。
日本人である私たちにもきちんとした説明はなかなか難しく、検索しつつ色々調べつつ、それを英語に通訳。
説明が終わった頃にはお雑煮のお餅はちょっと硬くなってしまいました。
それでもアメリカコロラド出身の彼には、お餅が柔らかいという感覚が今ひとつわからない様で、硬くても何ともない様で、ほっとしたこと今思い出しました。
海外在住の娘たちはチケットが安い時期に来るので、年末年始をずらし2月頃に帰国する事が多いので、我が家のお正月行事は2月が多く、その頃は市販のおせち料理(かまぼこ等)が安くて、とっても助かります笑
そのパートナーに日本のおせち料理を紹介するのが、毎回大変というか、とても面白いのです。
長女は彼に対して、料理一つ一つ丁寧に(子孫繁栄の子持ち昆布、出世魚の鰤の照り焼きなど)説明をします。
それに対して、次女のそれは超適当で、きんとんを不思議そうに見た彼に対して「That’s so sweet」
数の子には「That’s a big fish egg 」というあり様。
それを見てみんな大笑い。
甘いとか卵とかいう説明でなく、もっと他にあるでしょ!と流石の私たち家族も思い、みんなで必死の説明、お正月から英会話教室状態になりました。
日本人である私たちにもきちんとした説明はなかなか難しく、検索しつつ色々調べつつ、それを英語に通訳。
説明が終わった頃にはお雑煮のお餅はちょっと硬くなってしまいました。
それでもアメリカコロラド出身の彼には、お餅が柔らかいという感覚が今ひとつわからない様で、硬くても何ともない様で、ほっとしたこと今思い出しました。
海外在住の娘たちはチケットが安い時期に来るので、年末年始をずらし2月頃に帰国する事が多いので、我が家のお正月行事は2月が多く、その頃は市販のおせち料理(かまぼこ等)が安くて、とっても助かります笑
「おせちとわたし」 ノミネート作品04
実家と我が家は同じマンションの五階と九階。
夏が過ぎ、ハルメクからおせちの案内が届くと、母が吟味したコースに付箋がついた、おせちの申込書を父が我が家に届けてくれるのが、我が家の年越しの準備の始まりでした。
早割の期間が近づくと、母から注文したかの確認が入ります。
どれも美味しそうと、何度もパンフレットを眺めるけれど、結局毎年、実家と同じ物を、実家は父と母と帰省する妹の3人分、我が家は子供2人と私達の4人分一緒に注文するのがお決まりでした。
年末に実家に届いたお節を、我が家に届けてくれるのも父のお仕事。
タイミングを合わせて、冷凍庫から冷蔵庫へ。元旦は少しゆっくり目にそれぞれにお節を頂き、夕方、近所の神社に一緒に初詣にいく道すがら、今年のお節のこれが美味しかった、まだ半分残ってるわよなど感想を言い合う、これが長年の我が家のお正月でした。
去年の猛暑が続く9月の初めに、食いしん坊の父が他界し、母からハルメクのお節の声がけはありませんでした。
ハルメクのお節は父との思い出がいっぱいで、なかなか申込む気分に慣れなかったけれど、お屠蘇と一緒に、美味しそうにあれこれ箸を運ぶ姿を思い出し、実家の2人と我が家の4人を合わせた6人分を、私が注文しました。
年末が迫り、少し元気になった母。
お正月はどうしようかと、お祝いしないものかなと相談され、パパの好きそうなものが沢山あったから、一緒に食べようと思ってハルメク注文しといたよ、と伝えると母は少しほっとした笑顔になりました。
お正月は実家に集まって、じいじいにもちょっとずつおせちを取り分けて、パパこれ好きだったよね、とか言いながら一緒におせちを頂きました。
パンフレットを届けてくれる父はいなくなってしまったけれど、お料理の中身は毎年変わるけれど、毎年変わらない我が家のお正月は、ハルメクを囲んで、開けるよーの掛け声で蓋が開けられ、お屠蘇を飲めるようになった子供達と共に、一年が始まるんだろうな、と思います。
もちろん食いしん坊じいじいにも取り分けて。
夏が過ぎ、ハルメクからおせちの案内が届くと、母が吟味したコースに付箋がついた、おせちの申込書を父が我が家に届けてくれるのが、我が家の年越しの準備の始まりでした。
早割の期間が近づくと、母から注文したかの確認が入ります。
どれも美味しそうと、何度もパンフレットを眺めるけれど、結局毎年、実家と同じ物を、実家は父と母と帰省する妹の3人分、我が家は子供2人と私達の4人分一緒に注文するのがお決まりでした。
年末に実家に届いたお節を、我が家に届けてくれるのも父のお仕事。
タイミングを合わせて、冷凍庫から冷蔵庫へ。元旦は少しゆっくり目にそれぞれにお節を頂き、夕方、近所の神社に一緒に初詣にいく道すがら、今年のお節のこれが美味しかった、まだ半分残ってるわよなど感想を言い合う、これが長年の我が家のお正月でした。
去年の猛暑が続く9月の初めに、食いしん坊の父が他界し、母からハルメクのお節の声がけはありませんでした。
ハルメクのお節は父との思い出がいっぱいで、なかなか申込む気分に慣れなかったけれど、お屠蘇と一緒に、美味しそうにあれこれ箸を運ぶ姿を思い出し、実家の2人と我が家の4人を合わせた6人分を、私が注文しました。
年末が迫り、少し元気になった母。
お正月はどうしようかと、お祝いしないものかなと相談され、パパの好きそうなものが沢山あったから、一緒に食べようと思ってハルメク注文しといたよ、と伝えると母は少しほっとした笑顔になりました。
お正月は実家に集まって、じいじいにもちょっとずつおせちを取り分けて、パパこれ好きだったよね、とか言いながら一緒におせちを頂きました。
パンフレットを届けてくれる父はいなくなってしまったけれど、お料理の中身は毎年変わるけれど、毎年変わらない我が家のお正月は、ハルメクを囲んで、開けるよーの掛け声で蓋が開けられ、お屠蘇を飲めるようになった子供達と共に、一年が始まるんだろうな、と思います。
もちろん食いしん坊じいじいにも取り分けて。
「おせちとわたし」 ノミネート作品05
「おせち料理なんて大嫌い!お正月なんて来なければいいのに」
大晦日になると、母は決まってこの呪いの言葉を吐きながら三段重2組の準備に大忙しだった。
元旦には、同居する祖父母の元に叔父叔母家族が参集し新年会が催される。
来訪者は長男の嫁である母のおせちを食べ散らかし、祖父母だけに礼を言って帰って行く。
子どもの頃から見慣れた光景だった。
年と共に流石に親族の新年会はなくなったが、父の肝いりで家族だけの会は続いていた。
だがある秋の日、父に言い渡された。
「母さんにおせち料理はもうムリだ。長女のお前が何とかしてくれ」
いつの間にかお料理上手な母の認知症は、そこまで進んでいたのだ。
さりとて私は旅行業者。年末まで働いて、新年3日には初詣ツアーの添乗がある。
仕方なくネットで探し、有名料亭や料理研究家監修の見目麗しいおせち料理を取り寄せた。
三段重は元旦の食卓を華麗に飾ったが、皆ちょっと箸をつけるとあとは結婚式の「にらみ鯛」状態。
高かったのにもったいないと思いつつ、やむなく新年最初の生ごみの日に出すハメになった。
そんな時、ハルメクのおせち料理に出会った。
どうせまた……と思いながら「正月におせち料理がないのは寂しい」と言う父のために、「食卓の飾りにでもなれば」と全く期待せずに、人数より少なめの4人前を注文した。
ところが、あれよあれよという間に完食してしまう。
うそでしょう!
高齢の父も「美味しいねえ」とご満悦。
子どもたちも「これとこれがめちゃ美味しい」「来年もこのおせちが良いな」と嬉しそう。
それ以来ハルメクおせちは我家の定番になった。
一昨年父も鬼籍に入り、娘も嫁し、元旦は本当に小人数で過ごすことになった。
家族だけなのでおせち料理の手配をする必要もなくなり、仕事を引退したので時間はたっぷりある。
だが今年もまた色々な言い訳をしながら、ハルメクおせちを物色している私である。
大晦日になると、母は決まってこの呪いの言葉を吐きながら三段重2組の準備に大忙しだった。
元旦には、同居する祖父母の元に叔父叔母家族が参集し新年会が催される。
来訪者は長男の嫁である母のおせちを食べ散らかし、祖父母だけに礼を言って帰って行く。
子どもの頃から見慣れた光景だった。
年と共に流石に親族の新年会はなくなったが、父の肝いりで家族だけの会は続いていた。
だがある秋の日、父に言い渡された。
「母さんにおせち料理はもうムリだ。長女のお前が何とかしてくれ」
いつの間にかお料理上手な母の認知症は、そこまで進んでいたのだ。
さりとて私は旅行業者。年末まで働いて、新年3日には初詣ツアーの添乗がある。
仕方なくネットで探し、有名料亭や料理研究家監修の見目麗しいおせち料理を取り寄せた。
三段重は元旦の食卓を華麗に飾ったが、皆ちょっと箸をつけるとあとは結婚式の「にらみ鯛」状態。
高かったのにもったいないと思いつつ、やむなく新年最初の生ごみの日に出すハメになった。
そんな時、ハルメクのおせち料理に出会った。
どうせまた……と思いながら「正月におせち料理がないのは寂しい」と言う父のために、「食卓の飾りにでもなれば」と全く期待せずに、人数より少なめの4人前を注文した。
ところが、あれよあれよという間に完食してしまう。
うそでしょう!
高齢の父も「美味しいねえ」とご満悦。
子どもたちも「これとこれがめちゃ美味しい」「来年もこのおせちが良いな」と嬉しそう。
それ以来ハルメクおせちは我家の定番になった。
一昨年父も鬼籍に入り、娘も嫁し、元旦は本当に小人数で過ごすことになった。
家族だけなのでおせち料理の手配をする必要もなくなり、仕事を引退したので時間はたっぷりある。
だが今年もまた色々な言い訳をしながら、ハルメクおせちを物色している私である。
「おせちとわたし」 ノミネート作品06
もう、だいぶ前の話。
テレビで、和田アキ子さんが、毎年おせちを手作りしている事を知り、私もやってみようかなと、いきなり何種類も作った。
ふっくらしていない黒豆(笑)や飾り紅白かまぼこ、数の子、赤飯、なます、栗きんとん(栗は高いのでさつまいものみ使用)、田作り(仕上がりが硬すぎてカッチカチ) 、ついでにお雑煮など多種類作って、動作が遅く要領がわるい私は6時間くらい立ちっぱなし。
で、ぶっ倒れた。(いきなり倒れたのではなく、具合が悪くなり横になったらそのまま動けなくなった。)
次の日は動けず。
家族は褒めてくれたし、手作りだったので、それなりに美味しかった(と思う)が、二度と作っていない。
今は毎年、実家の母からのおせち(通販) を家族でありがたく元旦に頂いています(笑)
テレビで、和田アキ子さんが、毎年おせちを手作りしている事を知り、私もやってみようかなと、いきなり何種類も作った。
ふっくらしていない黒豆(笑)や飾り紅白かまぼこ、数の子、赤飯、なます、栗きんとん(栗は高いのでさつまいものみ使用)、田作り(仕上がりが硬すぎてカッチカチ) 、ついでにお雑煮など多種類作って、動作が遅く要領がわるい私は6時間くらい立ちっぱなし。
で、ぶっ倒れた。(いきなり倒れたのではなく、具合が悪くなり横になったらそのまま動けなくなった。)
次の日は動けず。
家族は褒めてくれたし、手作りだったので、それなりに美味しかった(と思う)が、二度と作っていない。
今は毎年、実家の母からのおせち(通販) を家族でありがたく元旦に頂いています(笑)
「おせちとわたし」 ノミネート作品07
おせちは、私の家族にとって特別な思い出の詰まった料理です。
特に祖母が毎年作るおせち料理は、私たち家族全員が楽しみにしているものでした。
しかし、ある年、そのおせち作りにまつわる出来事が私の心に深く刻まれることになりました。
その年は祖母が少し体調を崩していて、家族全員でおせち作りを手伝うことになりました。
母や叔母たちが中心となり、私も初めておせち作りに参加することに。
祖母はいつも、細かなレシピを覚えていて、見事におせちを仕上げていましたが、今年はその役割を家族で分担することになったのです。
まず、私は黒豆を担当しました。
祖母が「黒豆は、ふっくらと柔らかく煮るのがコツよ」と教えてくれました。
しかし、豆を火にかけたまま他の準備に夢中になってしまい、気が付いた時には鍋の中の黒豆が焦げ付いていました。
焦げた匂いが広がり、慌てて鍋を火からおろしましたが、すでに手遅れで、真っ黒に炭のようになった豆を前に、私は涙が出てきました。
その時、祖母がそっと私の肩に手を置いて、「大丈夫よ、失敗は誰にでもあるわ。私だって最初は何度も失敗したんだから」と優しく笑って言いました。
その言葉に少し救われた気持ちになり、再度チャレンジすることにしました。
今度は慎重に時間を見ながら、焦がさないように火加減を調整し、なんとか黒豆を無事に仕上げることができました。
大晦日の夜、家族全員が揃っておせちを囲んだ時、祖母は私が作った黒豆を一番に手に取り、「今年の黒豆は本当においしいわね」と褒めてくれました。
その瞬間、私は胸がいっぱいになり、思わず涙がこぼれました。
家族みんなが笑顔でその光景を見守り、笑い声が食卓に響きました。
その後も、おせち作りは私たち家族の年末の恒例行事となりましたが、あの年の出来事は今でも鮮明に覚えています。
祖母が教えてくれたのは、おせち作りの技術だけではなく、失敗を恐れずに挑戦することの大切さ、そして家族と共に過ごす時間の尊さでした。
おせちは、ただの料理ではなく、家族の絆を深める大切な時間。その思い出が、私の心をいつも温めてくれます。
特に祖母が毎年作るおせち料理は、私たち家族全員が楽しみにしているものでした。
しかし、ある年、そのおせち作りにまつわる出来事が私の心に深く刻まれることになりました。
その年は祖母が少し体調を崩していて、家族全員でおせち作りを手伝うことになりました。
母や叔母たちが中心となり、私も初めておせち作りに参加することに。
祖母はいつも、細かなレシピを覚えていて、見事におせちを仕上げていましたが、今年はその役割を家族で分担することになったのです。
まず、私は黒豆を担当しました。
祖母が「黒豆は、ふっくらと柔らかく煮るのがコツよ」と教えてくれました。
しかし、豆を火にかけたまま他の準備に夢中になってしまい、気が付いた時には鍋の中の黒豆が焦げ付いていました。
焦げた匂いが広がり、慌てて鍋を火からおろしましたが、すでに手遅れで、真っ黒に炭のようになった豆を前に、私は涙が出てきました。
その時、祖母がそっと私の肩に手を置いて、「大丈夫よ、失敗は誰にでもあるわ。私だって最初は何度も失敗したんだから」と優しく笑って言いました。
その言葉に少し救われた気持ちになり、再度チャレンジすることにしました。
今度は慎重に時間を見ながら、焦がさないように火加減を調整し、なんとか黒豆を無事に仕上げることができました。
大晦日の夜、家族全員が揃っておせちを囲んだ時、祖母は私が作った黒豆を一番に手に取り、「今年の黒豆は本当においしいわね」と褒めてくれました。
その瞬間、私は胸がいっぱいになり、思わず涙がこぼれました。
家族みんなが笑顔でその光景を見守り、笑い声が食卓に響きました。
その後も、おせち作りは私たち家族の年末の恒例行事となりましたが、あの年の出来事は今でも鮮明に覚えています。
祖母が教えてくれたのは、おせち作りの技術だけではなく、失敗を恐れずに挑戦することの大切さ、そして家族と共に過ごす時間の尊さでした。
おせちは、ただの料理ではなく、家族の絆を深める大切な時間。その思い出が、私の心をいつも温めてくれます。
「おせちとわたし」 ノミネート作品08
小さい頃から、お正月はいつも祖母が作ったお節を食べて過ごした。
海老、煮豆、昆布巻き、煮しめ、栗きんとん、伊達巻、紅白蒲鉾、酢の物、ごまめ、数の子・・・ 3段お重にぎっしり詰まった手作りお節。
大人になるにつれて、年始から営業しているお店も多く、外食で済ませたいと言う気持ちも多く、祖父母の家にわざと元旦の夜に行く事もあった。
それでも必ずお節が用意してあった。
「お節作るの大変だと思うから、もう来年からは作らなくていいよ〜」 と言った。
しかし、その次の年帰省してもやはりお節が用意されていた。
祖母が席を離れた時に、祖父が「最近ばあちゃんが認知が入って来てる。この前は通帳と印鑑無くして大変だった」と話があった。
そんな風には見えなかったので、少しビックリしたが、気にしながら祖母と話していると、話がみ合わない事があった。
でも私は、まだまだお節も作れるし大丈夫だろう。と言う気持ちで居たのだ。
その年の夏、祖母の認知症が進行し施設に入る事になり、そのタイミングを見計らったかの様に祖父が他界した。
家主が居なくなった空家を管理する事が出来ず、手放す事になり片付けをしていた時、祖母の部屋のテレビ台の中からチラシの裏紙に書かれた料理レシピが沢山出てきた。
お節のレシピもあり「みんな美味しいと言って食べてくれた」「味が少し薄かった。今度は調味料の量増やす」「昆布巻きの魚は鮭。鯖はダメ」とコメントも書いてあった。
私が鯖アレルギーなので、昆布巻きは鮭にして欲しいとお願いしていた事がメモに残されていたのを見て、祖母にお節を作らなくて良いと言ってしまった事に後悔をしていた。
そして次の年、私が祖母のレシピを見てお節を作り、祖母にプレゼントした。
「こんなに美味しい料理どこで習ったの?」 祖母は感動しながら食べてくれた。
これからは、毎年私がお節を作り祖母に恩返しをしていきたい。
海老、煮豆、昆布巻き、煮しめ、栗きんとん、伊達巻、紅白蒲鉾、酢の物、ごまめ、数の子・・・ 3段お重にぎっしり詰まった手作りお節。
大人になるにつれて、年始から営業しているお店も多く、外食で済ませたいと言う気持ちも多く、祖父母の家にわざと元旦の夜に行く事もあった。
それでも必ずお節が用意してあった。
「お節作るの大変だと思うから、もう来年からは作らなくていいよ〜」 と言った。
しかし、その次の年帰省してもやはりお節が用意されていた。
祖母が席を離れた時に、祖父が「最近ばあちゃんが認知が入って来てる。この前は通帳と印鑑無くして大変だった」と話があった。
そんな風には見えなかったので、少しビックリしたが、気にしながら祖母と話していると、話がみ合わない事があった。
でも私は、まだまだお節も作れるし大丈夫だろう。と言う気持ちで居たのだ。
その年の夏、祖母の認知症が進行し施設に入る事になり、そのタイミングを見計らったかの様に祖父が他界した。
家主が居なくなった空家を管理する事が出来ず、手放す事になり片付けをしていた時、祖母の部屋のテレビ台の中からチラシの裏紙に書かれた料理レシピが沢山出てきた。
お節のレシピもあり「みんな美味しいと言って食べてくれた」「味が少し薄かった。今度は調味料の量増やす」「昆布巻きの魚は鮭。鯖はダメ」とコメントも書いてあった。
私が鯖アレルギーなので、昆布巻きは鮭にして欲しいとお願いしていた事がメモに残されていたのを見て、祖母にお節を作らなくて良いと言ってしまった事に後悔をしていた。
そして次の年、私が祖母のレシピを見てお節を作り、祖母にプレゼントした。
「こんなに美味しい料理どこで習ったの?」 祖母は感動しながら食べてくれた。
これからは、毎年私がお節を作り祖母に恩返しをしていきたい。
「おせちとわたし」 ノミネート作品09
新年の朝、雪が静かに降る中、玄関のチャイムが鳴り響いた。
ドアを開けると、そこには重箱を大事に抱えた祖父が少し誇らしげな笑みを浮かべて立っていた。
「これ、持ってきたよ」と、祖父は重箱を私に差し出した。
その重さに驚きつつ、私はリビングのテーブルにそっと置いた。
祖母が他界して三年。
もう二度と手作りのおせちは食べられないと思っていた私は、祖父が手作りしたおせちだとは全く予想していなかった。
祖母が元気だった頃は、毎年おせちを作るのが恒例で、黒豆はふっくらと甘く、栗きんとんは黄金色に輝き、昆布巻きには祖母の秘伝の味付けが施されていた。
祖母が亡くなった時、その味はもう戻らないのだと思っていた。
料理を全くしてこなかった祖父が、どんな気持ちでこの一年を過ごしてきたのかを考えると、胸が締め付けられた。
「開けてごらん」と祖父が優しく言った。
私は重箱の蓋を開けた。
黒豆、栗きんとん、昆布巻き、だて巻き、煮しめが丁寧に詰められていた。
目頭が熱くなった。
「本当に、これ全部作ったの?」と尋ねると、祖父は照れながらうなずいた。
「最初は全然ダメだった。だて巻きなんて焦がして真っ黒になったし、黒豆もシワシワに。どうしてもあの味を届けたくて、おばあちゃんの残した料理帳を読んで、一年かけて練習したんだ」と。
不器用な祖父が、一生懸命に取り組んだ姿が目に浮かぶ。
「すごいよ。ありがとう、おじいちゃん…」と涙ながらに感謝を伝えた。
おせちの味は、おばあちゃんのものとは少し違ったけれど、温かく、優しい味だった。
黒豆は、ほんのり甘く、栗きんとんは少し不格好だけど、甘さと滑らかさが絶妙だった。
昆布巻きは、柔らかく煮込まれて、出汁の風味がしっかりと染みている。真心の詰まったおせちだった。
それからも、祖父は毎年おせちを作り続け、家族にとって新しいお正月の風物詩となった。
祖母を思い出しながら、祖父のおせちを囲んで、新たな年を迎えることができることが本当に幸せだ。
ドアを開けると、そこには重箱を大事に抱えた祖父が少し誇らしげな笑みを浮かべて立っていた。
「これ、持ってきたよ」と、祖父は重箱を私に差し出した。
その重さに驚きつつ、私はリビングのテーブルにそっと置いた。
祖母が他界して三年。
もう二度と手作りのおせちは食べられないと思っていた私は、祖父が手作りしたおせちだとは全く予想していなかった。
祖母が元気だった頃は、毎年おせちを作るのが恒例で、黒豆はふっくらと甘く、栗きんとんは黄金色に輝き、昆布巻きには祖母の秘伝の味付けが施されていた。
祖母が亡くなった時、その味はもう戻らないのだと思っていた。
料理を全くしてこなかった祖父が、どんな気持ちでこの一年を過ごしてきたのかを考えると、胸が締め付けられた。
「開けてごらん」と祖父が優しく言った。
私は重箱の蓋を開けた。
黒豆、栗きんとん、昆布巻き、だて巻き、煮しめが丁寧に詰められていた。
目頭が熱くなった。
「本当に、これ全部作ったの?」と尋ねると、祖父は照れながらうなずいた。
「最初は全然ダメだった。だて巻きなんて焦がして真っ黒になったし、黒豆もシワシワに。どうしてもあの味を届けたくて、おばあちゃんの残した料理帳を読んで、一年かけて練習したんだ」と。
不器用な祖父が、一生懸命に取り組んだ姿が目に浮かぶ。
「すごいよ。ありがとう、おじいちゃん…」と涙ながらに感謝を伝えた。
おせちの味は、おばあちゃんのものとは少し違ったけれど、温かく、優しい味だった。
黒豆は、ほんのり甘く、栗きんとんは少し不格好だけど、甘さと滑らかさが絶妙だった。
昆布巻きは、柔らかく煮込まれて、出汁の風味がしっかりと染みている。真心の詰まったおせちだった。
それからも、祖父は毎年おせちを作り続け、家族にとって新しいお正月の風物詩となった。
祖母を思い出しながら、祖父のおせちを囲んで、新たな年を迎えることができることが本当に幸せだ。
「おせちとわたし」 ノミネート作品10
教師だった父は勉学に厳しく、父の頭脳を受け継がなかった馬鹿な私は、父が嫌いでした。
成人してからは、門限5時の日々。遊びにも行けず、つまらない青春でした。
それでも、職場で知り合った人と結婚をし、姉妹二人の長女だった私は、家を継ぐ事もなく出ていきました。
息子が生まれ、父は、自分の子供に男の子がいなかったので大喜びし、孫の好物をもって、よく遊びに来ました。
年末になれば「おせち」を持ってきてくれましたが、正月に来る事はなく、私たち家族だけで頂いていました。
本当なら、私が「おせち」を持って、実家に行かなければいけないのに、いい加減で甘えてばかりいました。
そんな毎年の「おせち」も、25年目で途切れてしまいました。
年末、父が癌の余命1年宣告を受けてしまったのです。
私一人が説明を受け、父にも母にも言わず、苦悩の日々が始まりました。
12月から3か月間は入院していましたので、正月もなく、日々弱っていく病床の父を見ていると、もっともっと孝行すればよかったと後悔ばかりでした。
そして、その年の12月に、父は逝ってしまいました。
一人になってしまった母を、こちらに呼び寄せ、毎年「おせち」を頂き、「お父さん、私達ばかり美味しいおせちを頂いて、ごめんなさい」と、母と一緒に言いながら、仏壇にお供えをしていました。
そんな母も、父より20年も長生きをし、昨年の7月に亡くなりました。
年を重ねるにつれ、大切な人との別れが多くなり、切なくて涙が出てきます。
2人とも「栗きんとんと田つくり」が好きでした。
来年も美味しいおせちを楽しみに、今日も仏壇に手を合わせているのです。
成人してからは、門限5時の日々。遊びにも行けず、つまらない青春でした。
それでも、職場で知り合った人と結婚をし、姉妹二人の長女だった私は、家を継ぐ事もなく出ていきました。
息子が生まれ、父は、自分の子供に男の子がいなかったので大喜びし、孫の好物をもって、よく遊びに来ました。
年末になれば「おせち」を持ってきてくれましたが、正月に来る事はなく、私たち家族だけで頂いていました。
本当なら、私が「おせち」を持って、実家に行かなければいけないのに、いい加減で甘えてばかりいました。
そんな毎年の「おせち」も、25年目で途切れてしまいました。
年末、父が癌の余命1年宣告を受けてしまったのです。
私一人が説明を受け、父にも母にも言わず、苦悩の日々が始まりました。
12月から3か月間は入院していましたので、正月もなく、日々弱っていく病床の父を見ていると、もっともっと孝行すればよかったと後悔ばかりでした。
そして、その年の12月に、父は逝ってしまいました。
一人になってしまった母を、こちらに呼び寄せ、毎年「おせち」を頂き、「お父さん、私達ばかり美味しいおせちを頂いて、ごめんなさい」と、母と一緒に言いながら、仏壇にお供えをしていました。
そんな母も、父より20年も長生きをし、昨年の7月に亡くなりました。
年を重ねるにつれ、大切な人との別れが多くなり、切なくて涙が出てきます。
2人とも「栗きんとんと田つくり」が好きでした。
来年も美味しいおせちを楽しみに、今日も仏壇に手を合わせているのです。
「おせちとわたし」 ノミネート作品11
「お正月に帰るね。ちょっと会って欲しい人がいるんだ。」
年の暮れ。離れて暮らす母に電話をした。ちょうど四十歳になる年。これまで何度もお見合いをしてきたが、この度めでたく婚約。
「わかった。おせち作って待ってるね」
母の声は弾んでいた。
しかしなぜ神様はこうも意地悪なのだろう。帰省の二日前。突然「他に好きな人ができた」とまさかの失恋。それはもう寝耳に水。耳からホースを突っ込まれたくらいの衝撃。もう母に顔向けできなくなった。
お正月。憂鬱な気持ちで帰ると、台所に母がいた。
食卓には、山盛りの昆布巻き。見上げるほどの五段重。紅白がまぶしい蒲鉾。前日からきっと仕込みで大変だったのだろう。母の目元にはくっきりと隈があった。
「あれ?相手の方は?」
何も知らない母がこちらを見る。私も本当のことを言うのが怖くて、母のおせちにクレームをつけることに神経を集中させた。
「なんでこんなに昆布巻があるの?伊達巻が良かった。しかも きつく巻きすぎてなんか固いし。」
「……」
「こんな昆布巻、固くて食べられないよ」
すると「皆が『よろこぶ』ように昆布!ちょっと力みすぎて固く巻きすぎちゃったかな」と母。
その言葉にハッとした。私は昆布巻を作る母の気持ちをちゃんと理解していただろうか。
本当は喜びも不安もあったはず。
でも「うまくいきますように」って祈ってた。「うまくいけ」って思ってた。
だけど安易にそれが言えないから、きつく結んだ昆布巻はちょっと苦しくて、切なくて、ものすごく愛おしい。
「ごめん……フラれちゃった」
私が言葉を詰まらせると母はたった一言。
「また頑張ればいい」
私をギュッと抱きしめた。
この日食べたおせちは、涙でしょっぱく、ほろ苦く、でも最高に美味しかった。
年の暮れ。離れて暮らす母に電話をした。ちょうど四十歳になる年。これまで何度もお見合いをしてきたが、この度めでたく婚約。
「わかった。おせち作って待ってるね」
母の声は弾んでいた。
しかしなぜ神様はこうも意地悪なのだろう。帰省の二日前。突然「他に好きな人ができた」とまさかの失恋。それはもう寝耳に水。耳からホースを突っ込まれたくらいの衝撃。もう母に顔向けできなくなった。
お正月。憂鬱な気持ちで帰ると、台所に母がいた。
食卓には、山盛りの昆布巻き。見上げるほどの五段重。紅白がまぶしい蒲鉾。前日からきっと仕込みで大変だったのだろう。母の目元にはくっきりと隈があった。
「あれ?相手の方は?」
何も知らない母がこちらを見る。私も本当のことを言うのが怖くて、母のおせちにクレームをつけることに神経を集中させた。
「なんでこんなに昆布巻があるの?伊達巻が良かった。しかも きつく巻きすぎてなんか固いし。」
「……」
「こんな昆布巻、固くて食べられないよ」
すると「皆が『よろこぶ』ように昆布!ちょっと力みすぎて固く巻きすぎちゃったかな」と母。
その言葉にハッとした。私は昆布巻を作る母の気持ちをちゃんと理解していただろうか。
本当は喜びも不安もあったはず。
でも「うまくいきますように」って祈ってた。「うまくいけ」って思ってた。
だけど安易にそれが言えないから、きつく結んだ昆布巻はちょっと苦しくて、切なくて、ものすごく愛おしい。
「ごめん……フラれちゃった」
私が言葉を詰まらせると母はたった一言。
「また頑張ればいい」
私をギュッと抱きしめた。
この日食べたおせちは、涙でしょっぱく、ほろ苦く、でも最高に美味しかった。
「おせちとわたし」 ノミネート作品12
おせち料理なんて作ったことが無かった。
私の実家は肉屋で、一年のうち一番忙しいのが12月30・31日のいわゆる『暮売り』だ。
今でこそスーパーが元旦から営業し、買い置きなんて必要ないが、昔は正月3が日、下手をすると1週間も店が閉まっていたから、人々は正月のささやかな贅沢として、またお客に振舞う御馳走として、年末に肉を買い求めた。
うちの店も、暮は座る暇もないほど忙しかった。
はなから販売要員だった私は、友達からスキーに誘われても「ごめん、暮は肉屋なの。」と断るのが常で、結婚後もそれは変わらなかったし、ずっと続くと思っていた。
しかし、当時70歳の父を病魔が襲った。
自営業には健診がない。そのうえ身体が丈夫だった父は、病院に縁がなかった。
体調不良で受診した時には、既に手遅れ。余命3カ月の保証はないと宣告された。
父が入院し、母が店を閉めたのはその年の10月。
病院で対処療法を受けた後、父は家に帰ることを望み、母も自宅で最期を過ごさせてやりたいと訪問看護の手続きをとった。
「ねえ、おせち作ってみない?」初めてチキンを買って食べたクリスマスの後、母が言った。
「お父さんに最初で最後のおせち、食べさせてあげたいんだけど、手伝ってくれる?」
もちろん私に異論はない。そうなれば話は早い。母は調理師、私は門前の小僧だ。
母が買物リストを作り、私が材料を調達した。
その頃父は、一日の大半を寝て過ごしていたから、床ずれができないよう数時間ごとに体の向きを変えた。
着替えや清拭、食事の介助、そんな介護の合間に私たちは協力し、おせちをこしらえていった。
「おお、きれいだな。」完成したおせちを見て父は目を細めた。
「どれから食べる?」と母が顔を覗き込むと 「もったいなくて、食えねえよ。」父は言葉に詰まった。
自画自賛になるが、あの時作ったおせちは生涯最高だったと思う。
三人で食べた、最初で最後のおせちだ。
私の実家は肉屋で、一年のうち一番忙しいのが12月30・31日のいわゆる『暮売り』だ。
今でこそスーパーが元旦から営業し、買い置きなんて必要ないが、昔は正月3が日、下手をすると1週間も店が閉まっていたから、人々は正月のささやかな贅沢として、またお客に振舞う御馳走として、年末に肉を買い求めた。
うちの店も、暮は座る暇もないほど忙しかった。
はなから販売要員だった私は、友達からスキーに誘われても「ごめん、暮は肉屋なの。」と断るのが常で、結婚後もそれは変わらなかったし、ずっと続くと思っていた。
しかし、当時70歳の父を病魔が襲った。
自営業には健診がない。そのうえ身体が丈夫だった父は、病院に縁がなかった。
体調不良で受診した時には、既に手遅れ。余命3カ月の保証はないと宣告された。
父が入院し、母が店を閉めたのはその年の10月。
病院で対処療法を受けた後、父は家に帰ることを望み、母も自宅で最期を過ごさせてやりたいと訪問看護の手続きをとった。
「ねえ、おせち作ってみない?」初めてチキンを買って食べたクリスマスの後、母が言った。
「お父さんに最初で最後のおせち、食べさせてあげたいんだけど、手伝ってくれる?」
もちろん私に異論はない。そうなれば話は早い。母は調理師、私は門前の小僧だ。
母が買物リストを作り、私が材料を調達した。
その頃父は、一日の大半を寝て過ごしていたから、床ずれができないよう数時間ごとに体の向きを変えた。
着替えや清拭、食事の介助、そんな介護の合間に私たちは協力し、おせちをこしらえていった。
「おお、きれいだな。」完成したおせちを見て父は目を細めた。
「どれから食べる?」と母が顔を覗き込むと 「もったいなくて、食えねえよ。」父は言葉に詰まった。
自画自賛になるが、あの時作ったおせちは生涯最高だったと思う。
三人で食べた、最初で最後のおせちだ。
「おせちとわたし」 ノミネート作品13
私が子供だった頃、お正月、父の実家に新年の挨拶に行くと、大きなお皿に湯気がたった熱々の餃子がテーブルの上にどーんと置かれていました。
餃子が父方の家のおせちでした。
私は、祖母が作ったこの餃子が大好きで ひとりで抱えて食べていました。
そして祖父母や叔父 叔母の話しが始まります。
子供だった私には、ほとんど理解できませんでしたが 熱々の餃子を食べながら聞いていました。
父は、満州の引き揚げ者です。
父が子供の頃 満州では 正月やお祝い事は、餃子を食べて 家族や隣人でお祝いをしたそうです。
餃子は、日本の焼き餃子ではなく茹で餃子です。
粉を耳たぶ位の固さに練り、丸めて手の平くらいにのばします。
餡は、挽き肉と玉ねぎのみじん切りを塩胡椒で炒めます。
餡を包んで沸騰した湯の中に放り込みます。
浮き上がって来た餃子を酢醤油で食べます。
当時、満州の正月は、楽しい賑やかな正月だったと父や叔父は、にこやかに話していました。
しかし敗戦になり、父達家族は、着の身着のまま 屋根の無い船で 日本へ帰って来ました。
船の中では、食べる物もなく雨風にさらされて幼い弟達は亡くなったそうです。
そして日本では、父達家族が想像を越えた難が待ち構えていた話しをしていました。
正月に家族揃って餃子を食べられる日が来た時は、家族が皆 泣きながら熱々の餃子を食べたそうです。
祖母は、その話しになると必ず泣いていました。
そして「家族が笑顔で集まれる事が一番のご馳走ね」と言いました。
今、父や叔父 叔母達も亡くなり、餃子の話しをする人は、いなくなりました。
私は、祖母の味には到底かないませんが 茹で餃子を作ります。
そして 熱々の餃子を頬張る子供や孫達に 父の餃子の話しをします。
最後に「家族の笑顔が一番のご馳走」の話しをします。
餃子が父方の家のおせちでした。
私は、祖母が作ったこの餃子が大好きで ひとりで抱えて食べていました。
そして祖父母や叔父 叔母の話しが始まります。
子供だった私には、ほとんど理解できませんでしたが 熱々の餃子を食べながら聞いていました。
父は、満州の引き揚げ者です。
父が子供の頃 満州では 正月やお祝い事は、餃子を食べて 家族や隣人でお祝いをしたそうです。
餃子は、日本の焼き餃子ではなく茹で餃子です。
粉を耳たぶ位の固さに練り、丸めて手の平くらいにのばします。
餡は、挽き肉と玉ねぎのみじん切りを塩胡椒で炒めます。
餡を包んで沸騰した湯の中に放り込みます。
浮き上がって来た餃子を酢醤油で食べます。
当時、満州の正月は、楽しい賑やかな正月だったと父や叔父は、にこやかに話していました。
しかし敗戦になり、父達家族は、着の身着のまま 屋根の無い船で 日本へ帰って来ました。
船の中では、食べる物もなく雨風にさらされて幼い弟達は亡くなったそうです。
そして日本では、父達家族が想像を越えた難が待ち構えていた話しをしていました。
正月に家族揃って餃子を食べられる日が来た時は、家族が皆 泣きながら熱々の餃子を食べたそうです。
祖母は、その話しになると必ず泣いていました。
そして「家族が笑顔で集まれる事が一番のご馳走ね」と言いました。
今、父や叔父 叔母達も亡くなり、餃子の話しをする人は、いなくなりました。
私は、祖母の味には到底かないませんが 茹で餃子を作ります。
そして 熱々の餃子を頬張る子供や孫達に 父の餃子の話しをします。
最後に「家族の笑顔が一番のご馳走」の話しをします。
「おせちとわたし」 ノミネート作品14
高校を卒業後、就職した。全寮制の会社だった。
たくさんの同期に恵まれたけれど、ふるさとから離れて暮らすことは18才の私にはまだ寂しく、いつも帰りたいと布団の中で泣いていた。
仕事は想像を絶するほど厳しく、毎日怒鳴られ、50人ほどいた同期もあっという間にほとんどふるさとに帰っていった。
つらい日々、仕事を終えて寮に帰るといつも「おかえり、おつかれさん」と寮母さんが出迎えてくれ、泣いているわたしを部屋に招き入れてくれて話を聞いてくれ、そして生まれて初めて豆を引いたコーヒーを飲ませてくれた。
苦い、と思ったし美味しいとは思えなかったが香りがめっぽう良かった。それは幼いわたしにもわかった。
寮母さんのことはみんな親しみを込めて「おばちゃん」と呼んでおり、たぶん50代前半、おしゃれ、本棚には純文学がぎっしり、小さなキッチンには名前はわからないが美しいコーヒーを入れる道具がならんでいて、テレビの上には昨年虹の橋を渡ったと言う愛犬の写真が飾られていた。そして1人で暮らしていた。
わたしは自分の家が裕福でないこと、父が蒸発してしまって母が1人で必死に子育てと、父の両親の面倒を見ていること、そしてこの会社をやめたいけれど、それは母の負担になりわずかな仕送りもできなくなることなどをおばちゃんに聞いてもらっていた。
初めてのお正月、同期で1人だけ仕事だった。
疲れて寮に帰っておばちゃんに手渡されたものは小さな三段の重箱。それは1人用のおせちだった。口どりから全て手作りの美しいお節料理。
「お母さんのおせち食べたかったよね?よく頑張ったね、お母さんのおせちには敵わないけど食べてね」と言われ寮の部屋で1人おばちゃんのお節をいただいた。
つやつやの黒豆は母の得意料理、涙がぽろぽろこぼれて…ほんのりあまくて、せつなくて、悲しくて、幸せで、人生で一度きりしか味わったことのない特別なわたしだけのお節だった。
たくさんの同期に恵まれたけれど、ふるさとから離れて暮らすことは18才の私にはまだ寂しく、いつも帰りたいと布団の中で泣いていた。
仕事は想像を絶するほど厳しく、毎日怒鳴られ、50人ほどいた同期もあっという間にほとんどふるさとに帰っていった。
つらい日々、仕事を終えて寮に帰るといつも「おかえり、おつかれさん」と寮母さんが出迎えてくれ、泣いているわたしを部屋に招き入れてくれて話を聞いてくれ、そして生まれて初めて豆を引いたコーヒーを飲ませてくれた。
苦い、と思ったし美味しいとは思えなかったが香りがめっぽう良かった。それは幼いわたしにもわかった。
寮母さんのことはみんな親しみを込めて「おばちゃん」と呼んでおり、たぶん50代前半、おしゃれ、本棚には純文学がぎっしり、小さなキッチンには名前はわからないが美しいコーヒーを入れる道具がならんでいて、テレビの上には昨年虹の橋を渡ったと言う愛犬の写真が飾られていた。そして1人で暮らしていた。
わたしは自分の家が裕福でないこと、父が蒸発してしまって母が1人で必死に子育てと、父の両親の面倒を見ていること、そしてこの会社をやめたいけれど、それは母の負担になりわずかな仕送りもできなくなることなどをおばちゃんに聞いてもらっていた。
初めてのお正月、同期で1人だけ仕事だった。
疲れて寮に帰っておばちゃんに手渡されたものは小さな三段の重箱。それは1人用のおせちだった。口どりから全て手作りの美しいお節料理。
「お母さんのおせち食べたかったよね?よく頑張ったね、お母さんのおせちには敵わないけど食べてね」と言われ寮の部屋で1人おばちゃんのお節をいただいた。
つやつやの黒豆は母の得意料理、涙がぽろぽろこぼれて…ほんのりあまくて、せつなくて、悲しくて、幸せで、人生で一度きりしか味わったことのない特別なわたしだけのお節だった。
「おせちとわたし」 ノミネート作品15
「おせち」と聞くだけで、あの悪夢がよみがえります。
三年前の十二月三十日、初めて注文した冷凍おせちが宅配便で届きました。
奮発した二段重です。
冷蔵庫でゆっくり解凍した大晦日。
食卓は主役の登場を待つばかり。
「いいかぁ、運ぶぞぉ〜」
夫の声もうわずっています。
冷蔵庫から二段重をうやうやしく取り出し、振り向いた瞬間に、それは起きました。
彼がよろけて、お重を落としてしまったのです。
蓋が開き、台所の床にぶちまけられた豪華なおせち。私たちは言葉もなく、ただ呆然と眺めるばかりでした。
後始末をどうしたかは言わぬが花でしょう。
それ以来、「おせち」はわが家の禁句となりました。
三年前の十二月三十日、初めて注文した冷凍おせちが宅配便で届きました。
奮発した二段重です。
冷蔵庫でゆっくり解凍した大晦日。
食卓は主役の登場を待つばかり。
「いいかぁ、運ぶぞぉ〜」
夫の声もうわずっています。
冷蔵庫から二段重をうやうやしく取り出し、振り向いた瞬間に、それは起きました。
彼がよろけて、お重を落としてしまったのです。
蓋が開き、台所の床にぶちまけられた豪華なおせち。私たちは言葉もなく、ただ呆然と眺めるばかりでした。
後始末をどうしたかは言わぬが花でしょう。
それ以来、「おせち」はわが家の禁句となりました。
「おせちとわたし」 ノミネート作品16
「おせち」というものをこしらえたのは、結婚後26年経ってからのことでした。
私の嫁ぎ先は造り酒屋。古くからのしきたりで年末年始にすべきことは沢山あったにも拘らず、なぜか「おせち」というものを作る家風では無かったのです。
育った実家は県外で家業も違っていたので、年末年始は親族が一堂に会してわやわやと料理を囲んで賑やかに過ごしたのですが…嫁いだこの家は、何と大晦日は年越し蕎麦だけ、三が日は雑煮だけ、という本当に寂しい(つまらない)食卓だったのです。
つまり嫁いで初めての正月に絶大なカルチャーショックを受けたわけです。
まぁそれは、家業柄多忙な男衆の食事事情に合わせた名残なので仕方がないとは思いつつ、私は(何と空しい正月…)と毎年そう思いながら25年間その家風の中で暮らしてきたのでした。
そうして25年、銀婚式を迎えた2カ月後。夫が、突然逝ってしまいました。
何が起きたの?これからどうすれば良いの?会社は?!子供たちは?!
途方に暮れている私に追い打ちを掛けて、親族との確執が起き、そして私は婚家を離れました。
大きなお屋敷だった婚家から、狭くて小さなマンションの中で仏壇の中のお位牌と暮らす日々。
時にふと号泣することもあったし一日中ボーっと過ごす日もあったけれど、時は否応なく過ぎていきます。
その年の正月は、帰省した子供たちと少し寂しい手料理だけで新年を迎えました。
そして翌年。喪が明けた正月。私は初めて「おせち」というものを手作りしたのです!
大したものではなかったけれど、煮物の人参を花形に切り、卵を10個茹でて錦玉子を作り、紅白のなますを作り、重箱に詰めて蒲鉾を飾りました。
わぁ!おせち料理ができた!…わくわくして嬉しかった!!嬉しくて、それらをてんこ盛りにして夫にお供えしました(笑)
夫も初めて食べる私の「手作りおせち」です。
26年目のおせち、きっと夫は美味しいね〜と言ってくれたと思います。
私の嫁ぎ先は造り酒屋。古くからのしきたりで年末年始にすべきことは沢山あったにも拘らず、なぜか「おせち」というものを作る家風では無かったのです。
育った実家は県外で家業も違っていたので、年末年始は親族が一堂に会してわやわやと料理を囲んで賑やかに過ごしたのですが…嫁いだこの家は、何と大晦日は年越し蕎麦だけ、三が日は雑煮だけ、という本当に寂しい(つまらない)食卓だったのです。
つまり嫁いで初めての正月に絶大なカルチャーショックを受けたわけです。
まぁそれは、家業柄多忙な男衆の食事事情に合わせた名残なので仕方がないとは思いつつ、私は(何と空しい正月…)と毎年そう思いながら25年間その家風の中で暮らしてきたのでした。
そうして25年、銀婚式を迎えた2カ月後。夫が、突然逝ってしまいました。
何が起きたの?これからどうすれば良いの?会社は?!子供たちは?!
途方に暮れている私に追い打ちを掛けて、親族との確執が起き、そして私は婚家を離れました。
大きなお屋敷だった婚家から、狭くて小さなマンションの中で仏壇の中のお位牌と暮らす日々。
時にふと号泣することもあったし一日中ボーっと過ごす日もあったけれど、時は否応なく過ぎていきます。
その年の正月は、帰省した子供たちと少し寂しい手料理だけで新年を迎えました。
そして翌年。喪が明けた正月。私は初めて「おせち」というものを手作りしたのです!
大したものではなかったけれど、煮物の人参を花形に切り、卵を10個茹でて錦玉子を作り、紅白のなますを作り、重箱に詰めて蒲鉾を飾りました。
わぁ!おせち料理ができた!…わくわくして嬉しかった!!嬉しくて、それらをてんこ盛りにして夫にお供えしました(笑)
夫も初めて食べる私の「手作りおせち」です。
26年目のおせち、きっと夫は美味しいね〜と言ってくれたと思います。
「おせちとわたし」 ノミネート作品17
あれは私が24歳の時のクリスマスイブだった。
事の発端は夫の一言から始まった。
婚約中だった夫は秋に徳島から東京に転勤し、お正月は私が夫のところへ出向くことになっていた。
その日、電話で取り留めのない話をしていると、夫が突然、「君の手作りのおせちが食べたいなあ。僕、ごまめと栗きんとんが好きなんよ」と、言い出した。
私は一瞬ドキッとしたが、「私も大好き。作って持って行くわ」と、話を合わせた。
電話を切ってから、私は心の中で呟いた。
──ごまめって、どんな豆?
栗きんとんって、何なん?──。
私は夫と付き合い始めた頃に特技を聞かれて、その場しのぎで「料理」と答えた。
そして得意料理は何かと問われ、思い付きで、「おせち」と口走ってしまったのだ。
私は電話の一部始終を母に報告すると、母は目が点になった。
「カレーしか作ったことがないあんたにそんな難しいもん、出来るはずがないやろ」
私は母に非難囂囂を浴びせられた。
それから大晦日まで、私は毎日買い出しに付き合わされ、家では一日中台所に監禁された。
「あんたはほんまにお調子者なんやから。尻拭いせなあかん親の身にも、なってみな!」
母の小言が飛び交う中で、私は、母のサツマイモを裏ごししている姿を眺めながら、おせちって、すごく手間のかかるものだということを実感した。
と同時に店頭で売られているプロの作ったものがどうしてあんなに高価なのかも腑に落ちた。
そしていよいよ元旦が来た。私は三段重を抱え東京に向かった。
重箱の蓋を開けた瞬間、夫は感嘆の声を上げた。
結婚して41年の歳月が経ったけれど、私は今でもあの時の夫の表情が目に浮かんでくる。
私のおせち神話は、日々の私の料理から早々に夫にバレた。
母が高齢になりおせちが作れなくなってからは、毎年お取り寄せをするようになった。
今年の元旦、夫は豪華なおせちを見て、苦笑いしながら言った。
「君の一番の得意技はなあ、『大嘘がつけること』だよ」
事の発端は夫の一言から始まった。
婚約中だった夫は秋に徳島から東京に転勤し、お正月は私が夫のところへ出向くことになっていた。
その日、電話で取り留めのない話をしていると、夫が突然、「君の手作りのおせちが食べたいなあ。僕、ごまめと栗きんとんが好きなんよ」と、言い出した。
私は一瞬ドキッとしたが、「私も大好き。作って持って行くわ」と、話を合わせた。
電話を切ってから、私は心の中で呟いた。
──ごまめって、どんな豆?
栗きんとんって、何なん?──。
私は夫と付き合い始めた頃に特技を聞かれて、その場しのぎで「料理」と答えた。
そして得意料理は何かと問われ、思い付きで、「おせち」と口走ってしまったのだ。
私は電話の一部始終を母に報告すると、母は目が点になった。
「カレーしか作ったことがないあんたにそんな難しいもん、出来るはずがないやろ」
私は母に非難囂囂を浴びせられた。
それから大晦日まで、私は毎日買い出しに付き合わされ、家では一日中台所に監禁された。
「あんたはほんまにお調子者なんやから。尻拭いせなあかん親の身にも、なってみな!」
母の小言が飛び交う中で、私は、母のサツマイモを裏ごししている姿を眺めながら、おせちって、すごく手間のかかるものだということを実感した。
と同時に店頭で売られているプロの作ったものがどうしてあんなに高価なのかも腑に落ちた。
そしていよいよ元旦が来た。私は三段重を抱え東京に向かった。
重箱の蓋を開けた瞬間、夫は感嘆の声を上げた。
結婚して41年の歳月が経ったけれど、私は今でもあの時の夫の表情が目に浮かんでくる。
私のおせち神話は、日々の私の料理から早々に夫にバレた。
母が高齢になりおせちが作れなくなってからは、毎年お取り寄せをするようになった。
今年の元旦、夫は豪華なおせちを見て、苦笑いしながら言った。
「君の一番の得意技はなあ、『大嘘がつけること』だよ」
「おせちとわたし」 ノミネート作品18
父は昔から『超』がつく程、几帳面だ。
どんなに些細な予定でもカレンダーに逐一書き込む。
例えば12月30日は『お煮しめ作り』。その前日には『芋の皮をむく』とまで。
「そんなの書くまでもない」と私が言うと「忘れたら困るだろ」とムキになる。
そんなところも含めて愛すべき父だった。
しかし年の暮れ。父が脳梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。
突然のことに家族は大ショック。冷蔵庫には、父が準備したおせちと、深い悲しみだけが残された。
だけど奇跡が起きた。
葬儀を終えたあと、突然、父のスマートフォンが鳴り響いた。
こんな時に一体誰が。
だが、おそるおそる画面を覗いて、言葉を失った。
『お年玉とお煮しめを娘宅に届ける』
それはスケジュール帳のアラーム機能。
つまり父が生前設定したものだった。
実を言うと今年は出産間近で、正月の帰省は見送ることにしていた。
だけど父は、こっそり、会いに行こうとしていた。
まるで天国からのあけましておめでとう。
思ってもいなかった父の計らいに私は胸がいっぱいになった。
今なら言える気がする。
私を愛し、育ててくれた父に。
父ちゃん、育ててくれてありがとう。
お煮しめは届かなかったけど、父ちゃんの思いはちゃんと届いたよ、と。
どんなに些細な予定でもカレンダーに逐一書き込む。
例えば12月30日は『お煮しめ作り』。その前日には『芋の皮をむく』とまで。
「そんなの書くまでもない」と私が言うと「忘れたら困るだろ」とムキになる。
そんなところも含めて愛すべき父だった。
しかし年の暮れ。父が脳梗塞で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。
突然のことに家族は大ショック。冷蔵庫には、父が準備したおせちと、深い悲しみだけが残された。
だけど奇跡が起きた。
葬儀を終えたあと、突然、父のスマートフォンが鳴り響いた。
こんな時に一体誰が。
だが、おそるおそる画面を覗いて、言葉を失った。
『お年玉とお煮しめを娘宅に届ける』
それはスケジュール帳のアラーム機能。
つまり父が生前設定したものだった。
実を言うと今年は出産間近で、正月の帰省は見送ることにしていた。
だけど父は、こっそり、会いに行こうとしていた。
まるで天国からのあけましておめでとう。
思ってもいなかった父の計らいに私は胸がいっぱいになった。
今なら言える気がする。
私を愛し、育ててくれた父に。
父ちゃん、育ててくれてありがとう。
お煮しめは届かなかったけど、父ちゃんの思いはちゃんと届いたよ、と。
「おせちとわたし」 ノミネート作品19
私が高校生だったころ、我が家では「究極のオリジナルおせち」を作るという壮大な挑戦が始まりました。
家族全員で話し合い、それぞれが好きな料理を2品ずつ提案し、それをおせち料理として盛り込むことに決めたのです。
父はエビチリとだし巻き卵、母は味噌カツとミルフィーユ、弟はピザとお寿司、そして私はボロネーゼとバスクチーズケーキを選びました。
伝統的なおせちからは完全に逸脱したメニューでした。
選んだメニューを各々が自作し重箱の一段に詰めることとなりました。
当日、重箱の蓋を開けた瞬間、みんなの顔には驚きと笑いが広がりました。
ハチャメチャなおせちで我が家に遊びに来ていた祖母は「これが新時代のおせちなのね」と微笑みながら、みんなでその斬新な料理を楽しみました。
しかし、その後、祖母がふと「でもやっぱり、黒豆や数の子、昆布巻きが恋しいわね」とつぶやきました。
私たちも同じ気持ちを感じ始めた頃でした。
そしてふざけもするが抜かりない我が家、他の段には伝統的なおせちをしっかりと作っているのでした。
そしていつものおせちをみんなで囲む中で、一つ一つの料理に意味がありよい新年になるようにと家族で食べることに意味があるのだと少し感慨深くなりました。
それからの我が家の新年は元旦に伝統的なおせち、二日にみんなで作ったオリジナルおせちを食べて楽しく新年を過ごしています(笑)。
家族全員で話し合い、それぞれが好きな料理を2品ずつ提案し、それをおせち料理として盛り込むことに決めたのです。
父はエビチリとだし巻き卵、母は味噌カツとミルフィーユ、弟はピザとお寿司、そして私はボロネーゼとバスクチーズケーキを選びました。
伝統的なおせちからは完全に逸脱したメニューでした。
選んだメニューを各々が自作し重箱の一段に詰めることとなりました。
当日、重箱の蓋を開けた瞬間、みんなの顔には驚きと笑いが広がりました。
ハチャメチャなおせちで我が家に遊びに来ていた祖母は「これが新時代のおせちなのね」と微笑みながら、みんなでその斬新な料理を楽しみました。
しかし、その後、祖母がふと「でもやっぱり、黒豆や数の子、昆布巻きが恋しいわね」とつぶやきました。
私たちも同じ気持ちを感じ始めた頃でした。
そしてふざけもするが抜かりない我が家、他の段には伝統的なおせちをしっかりと作っているのでした。
そしていつものおせちをみんなで囲む中で、一つ一つの料理に意味がありよい新年になるようにと家族で食べることに意味があるのだと少し感慨深くなりました。
それからの我が家の新年は元旦に伝統的なおせち、二日にみんなで作ったオリジナルおせちを食べて楽しく新年を過ごしています(笑)。
「おせちとわたし」 ノミネート作品20
生まれつき足が1本なかった保護猫と迎える、初めてのお正月を前に、おせちを全部手作りしました。
旦那さんの好きな物、私の好きな物…おせちの枠を超えて、お重につめれば何でもOKの品々でしたが。
そしてもちろん、猫の分のおせちも作らねば!
うちに来たときは手の平に乗るくらいに小さかったのに、順調に育って若干太り気味…?になってくれていたので、普段はキャットフードです。
でもお正月は一緒におせちを食べたくで、彼女の大好きなチキンと卵を用意してあげようと準備していました。
すると、生の状態でも気配と匂いを察知し、足りない足でも器用にキッチンに飛び乗ってきました。
生肉をくわえようとするので「だめ〜!」と取り上げると「う〜っ!」と抗議。
「だめ〜!」「う〜っ!」を繰り返しつつ、何とか生肉を口に入れることから守り、彼女も諦めてキッチンから降りました。
やれやれ…ほっとして調理再開し、少ししておとなしくなった彼女はどうしてる…?と振り向くと…。
テーブルに準備しておいた大皿の上にちんまり座り、出来上がりを待っていたのです。
もう大笑い!別の部屋にいた旦那さんもやってきてその光景に大爆笑!
可愛すぎる待ち姿勢に、抱きしめずにはいられませんでした。
大晦日から、ごちそうを食べながら紅白等を見てまったりするのが我が家流。
彼女も大晦日からしっかり大好きなチキンをはむはむして、ぐっすり。ちょっと早い初夢だったのかな。
そんな彼女は、生まれつきの心臓病のため、わずか2年で天国へ。
一緒に過ごしたお正月は一生の思い出です。
天国でまた、一緒におせちチキンを食べようね。大皿の上で待っててね!
旦那さんの好きな物、私の好きな物…おせちの枠を超えて、お重につめれば何でもOKの品々でしたが。
そしてもちろん、猫の分のおせちも作らねば!
うちに来たときは手の平に乗るくらいに小さかったのに、順調に育って若干太り気味…?になってくれていたので、普段はキャットフードです。
でもお正月は一緒におせちを食べたくで、彼女の大好きなチキンと卵を用意してあげようと準備していました。
すると、生の状態でも気配と匂いを察知し、足りない足でも器用にキッチンに飛び乗ってきました。
生肉をくわえようとするので「だめ〜!」と取り上げると「う〜っ!」と抗議。
「だめ〜!」「う〜っ!」を繰り返しつつ、何とか生肉を口に入れることから守り、彼女も諦めてキッチンから降りました。
やれやれ…ほっとして調理再開し、少ししておとなしくなった彼女はどうしてる…?と振り向くと…。
テーブルに準備しておいた大皿の上にちんまり座り、出来上がりを待っていたのです。
もう大笑い!別の部屋にいた旦那さんもやってきてその光景に大爆笑!
可愛すぎる待ち姿勢に、抱きしめずにはいられませんでした。
大晦日から、ごちそうを食べながら紅白等を見てまったりするのが我が家流。
彼女も大晦日からしっかり大好きなチキンをはむはむして、ぐっすり。ちょっと早い初夢だったのかな。
そんな彼女は、生まれつきの心臓病のため、わずか2年で天国へ。
一緒に過ごしたお正月は一生の思い出です。
天国でまた、一緒におせちチキンを食べようね。大皿の上で待っててね!
「おせちとわたし」 ノミネート作品21
平成四年の十二月のカレンダーの裏にメモ 書きされた昆布巻きのレシピは、三十年前、六十四歳で乳がんで他界した夫の母との温かで懐かしい思い出です。
義母はまた毎年お節料理に全身全霊を傾ける人でした。
歳の暮れには食材の買い出しから始まり、お煮しめは薄味のものからひとつひとつ煮て、昆布巻きもコトコトと…出来上がったら、涼しいところに机を出して、お重に詰めた沢山のお節料理を並べます。
お正月三が日かけて、家族みんなで頂く。それが夫の実家のお正月でした。
平成四年の暮れは、そんな義母が病を患い、今年はお節作りは難しいかもしれないというほど病状が進んでいた頃でした。
義母に少しでも元気になって欲しい。そんな思いで子どもたちで話し合い、義母の数あるお節メニューの中から一〜二品づつ選び、義母の指導の下、自分たちで作って正月に持ち寄ることに決めました。
私の担当は、昆布巻き、その時に電話で母から作り方を聞き、メモしたのが平成四年のカレンダーの裏でした。
義母の昆布巻きは、ちくわ、ごぼう、鮭、焼き豆腐、かんぴょうなどの具材を、六センチくらいに切った昆布に其々巻いて、糸でつないで長時間コトコト大鍋で煮込みます。
昆布をふやかし、何度もお湯でゆでこぼすところから始まり、時短追及の今では考えられない時間と労力をかけたレシピでしたが、様々な具材の味が昆布に沁み込んで、素朴で優しい昆布巻きでした。
レシピメモには「ひたひたの水」をと書いたところを二重線で消して「たっぷりの水でことこと」に、「酒、砂糖お玉一杯、醤油お玉一杯強」など、豪快で優しかった義母が電話口で、若い嫁に わかりやすくと考え考え話してくれた様子が 伝わってきます。
と同時に「沸いたら」「コトコト煮て」「味を平均に」義母の口述とおりにひたすら書きとっている新米主婦の自分にも少しほろっとしてしまったりして…(笑)
私のレシピファイルに挟まれたカレンダーの裏に書かれた昆布巻きのメモ、もうセピア色になってしまいましたが、何だか義母との二人だけの優しい思い出が詰まっていて今でも捨てられずにいます。
数年前から我が家もお節は作らず買うものなってしまいましたが、今年は懐かしの昆布巻きをちょっと作ってみようかな。
義母はまた毎年お節料理に全身全霊を傾ける人でした。
歳の暮れには食材の買い出しから始まり、お煮しめは薄味のものからひとつひとつ煮て、昆布巻きもコトコトと…出来上がったら、涼しいところに机を出して、お重に詰めた沢山のお節料理を並べます。
お正月三が日かけて、家族みんなで頂く。それが夫の実家のお正月でした。
平成四年の暮れは、そんな義母が病を患い、今年はお節作りは難しいかもしれないというほど病状が進んでいた頃でした。
義母に少しでも元気になって欲しい。そんな思いで子どもたちで話し合い、義母の数あるお節メニューの中から一〜二品づつ選び、義母の指導の下、自分たちで作って正月に持ち寄ることに決めました。
私の担当は、昆布巻き、その時に電話で母から作り方を聞き、メモしたのが平成四年のカレンダーの裏でした。
義母の昆布巻きは、ちくわ、ごぼう、鮭、焼き豆腐、かんぴょうなどの具材を、六センチくらいに切った昆布に其々巻いて、糸でつないで長時間コトコト大鍋で煮込みます。
昆布をふやかし、何度もお湯でゆでこぼすところから始まり、時短追及の今では考えられない時間と労力をかけたレシピでしたが、様々な具材の味が昆布に沁み込んで、素朴で優しい昆布巻きでした。
レシピメモには「ひたひたの水」をと書いたところを二重線で消して「たっぷりの水でことこと」に、「酒、砂糖お玉一杯、醤油お玉一杯強」など、豪快で優しかった義母が電話口で、若い嫁に わかりやすくと考え考え話してくれた様子が 伝わってきます。
と同時に「沸いたら」「コトコト煮て」「味を平均に」義母の口述とおりにひたすら書きとっている新米主婦の自分にも少しほろっとしてしまったりして…(笑)
私のレシピファイルに挟まれたカレンダーの裏に書かれた昆布巻きのメモ、もうセピア色になってしまいましたが、何だか義母との二人だけの優しい思い出が詰まっていて今でも捨てられずにいます。
数年前から我が家もお節は作らず買うものなってしまいましたが、今年は懐かしの昆布巻きをちょっと作ってみようかな。
「おせちとわたし」 ノミネート作品22
黒豆は、小さい頃から私の好きなおせち料理のひとつだ。
「”マメに仕事や勉強が出来るように”とか、”いつまでも艶やかで長生きできるように”って意味があるんよ」
母が毎年そんな風に言いながら作る黒豆は、ツヤツヤのぴかぴか、子供心に綺麗だなぁと思いながら口に運んでいた。
進学し実家を離れてからも、年末年始の帰省から自分のアパートへ戻る際にはタッパーに黒豆を詰めてもらった。
私は今、結婚して夫の実家で暮らしている。
同居して初めての年末はコロナ禍で、遠方にある実家への帰省は見送ることにした。
義家族も、親戚まわりは控えて家族だけでのんびりやろうという。
気楽な気持ちになりつつ、ふと私は自分で黒豆を煮ようと思い立った。
この時なぜか上手く出来る気満々だった、自分で作ったことは一度もないのに。
大晦日の夜、初めて作った黒豆はシワシワで色もくすんでいた。
あちゃー、と思いつつひと粒つまんでみると、味は悪くない。
(悪くないけど、なぁ…) 項垂れていると、夫が台所に入ってきた。
「おー、いい匂い。味見していい?」
「いいよ、でも失敗した…」
夫は黒豆を数粒つまんで口に運んだ。
「どこが?美味しいよ」
「だってシワシワだもん」
「え、いいんじゃないの?黒豆って”シワシワになるまで長生きできる”みたいな意味でしょ」
見た目を気にする私に、なんでもないことのように夫が言った。
ん?私の知っている黒豆の意味とちょっと違うよ? そのことを告げると、
「じゃあついでに”見た目よりも味わいを大切にできるように”って意味を込めよう」
「何だそりゃ」
夫の言葉に思わず笑ってしまった。
「ものは言いよう、美味しいからOK!」
母の黒豆のように綺麗ではないけれど、まあこれはこれでいいか。
夫が黒豆に込めた自由な”いわれ”に、私はちょっと前向きな気持ちになれた。
「”マメに仕事や勉強が出来るように”とか、”いつまでも艶やかで長生きできるように”って意味があるんよ」
母が毎年そんな風に言いながら作る黒豆は、ツヤツヤのぴかぴか、子供心に綺麗だなぁと思いながら口に運んでいた。
進学し実家を離れてからも、年末年始の帰省から自分のアパートへ戻る際にはタッパーに黒豆を詰めてもらった。
私は今、結婚して夫の実家で暮らしている。
同居して初めての年末はコロナ禍で、遠方にある実家への帰省は見送ることにした。
義家族も、親戚まわりは控えて家族だけでのんびりやろうという。
気楽な気持ちになりつつ、ふと私は自分で黒豆を煮ようと思い立った。
この時なぜか上手く出来る気満々だった、自分で作ったことは一度もないのに。
大晦日の夜、初めて作った黒豆はシワシワで色もくすんでいた。
あちゃー、と思いつつひと粒つまんでみると、味は悪くない。
(悪くないけど、なぁ…) 項垂れていると、夫が台所に入ってきた。
「おー、いい匂い。味見していい?」
「いいよ、でも失敗した…」
夫は黒豆を数粒つまんで口に運んだ。
「どこが?美味しいよ」
「だってシワシワだもん」
「え、いいんじゃないの?黒豆って”シワシワになるまで長生きできる”みたいな意味でしょ」
見た目を気にする私に、なんでもないことのように夫が言った。
ん?私の知っている黒豆の意味とちょっと違うよ? そのことを告げると、
「じゃあついでに”見た目よりも味わいを大切にできるように”って意味を込めよう」
「何だそりゃ」
夫の言葉に思わず笑ってしまった。
「ものは言いよう、美味しいからOK!」
母の黒豆のように綺麗ではないけれど、まあこれはこれでいいか。
夫が黒豆に込めた自由な”いわれ”に、私はちょっと前向きな気持ちになれた。
「おせちとわたし」 ノミネート作品23
それは冷たい海風が吹く20数年前の年末。
私と夫、私の両親の4人で、茨城の港にある小さな魚市場に、正月の買い出しに出かけたときのことです。
狭い市場には、水揚げしたばかりの地魚や脂ののったマグロ等が所狭しと並び、お客さんが押し合いへしあい。
その熱気と、鉢巻きに前掛けの漁師さんの大声で、さながらフェスの様です。
「もうちょっと負かんない?」
「わがった!持ってげ」と地元弁でのコール&レスポンスが起きています。
早速私達も参戦し、新鮮な魚と気前の良いお店を探すべく前進。
魚に加え、母お手製の松前漬けに必要なスルメイカも買う予定でした。
しかし、普段静かに暮らす両親は、魚の柵一つ二つを買うと、
「疲れたね、これでいいね」とスルメイカを諦め車に戻ろうとしています。
「えっ」。
大混雑の駐車場で両親が迷子にならないよう大急ぎで駐車場に向かう私達。
しかし、醤油や味醂、ちょっぴりお酒のきいた、美味しい松前漬けも諦めきれません。
そんな私達の足元に現れたのは…。1枚のスルメイカ。
「でしょ」「拾っちゃう?」、目と目で通じ合う二人。
一歩一歩両親が近づいてきます。
サッと夫が車のミラーにスルメイカを乗せ、私は両親に話しかけて時間稼ぎ。
スルメイカに両親が気づきます。
「わー!イカだー」と素直な母に「もらっちゃおう」とちゃっかり者の父。
帰りの車内では、「あれなんだったんだろうね」「神様の贈り物ですかね」と私と夫の小芝居が始まります。
すると、「そうだね、神様。宝物だ」。マジか…。疑問を持たない両親に驚く私達。
「うん。それでいい。いや、それがいい」、またもや目と目で通じ合いました。
震災の津波を受けたあの市場は建て替えられましたが、両親の胸の中で、あのスルメは宝物のまま生きています。
本当のことを打ち明けたら、父は「1本取られた!」というかもしれません。
私は「10本だよ、イカだけにね」と返すつもりです。
そしてこの内緒の時間がずっと続くことと、年々老いていく両親と、あの松前漬けの話をする年末がこれから何度も繰り返すことを私も夫も願っています。
私と夫、私の両親の4人で、茨城の港にある小さな魚市場に、正月の買い出しに出かけたときのことです。
狭い市場には、水揚げしたばかりの地魚や脂ののったマグロ等が所狭しと並び、お客さんが押し合いへしあい。
その熱気と、鉢巻きに前掛けの漁師さんの大声で、さながらフェスの様です。
「もうちょっと負かんない?」
「わがった!持ってげ」と地元弁でのコール&レスポンスが起きています。
早速私達も参戦し、新鮮な魚と気前の良いお店を探すべく前進。
魚に加え、母お手製の松前漬けに必要なスルメイカも買う予定でした。
しかし、普段静かに暮らす両親は、魚の柵一つ二つを買うと、
「疲れたね、これでいいね」とスルメイカを諦め車に戻ろうとしています。
「えっ」。
大混雑の駐車場で両親が迷子にならないよう大急ぎで駐車場に向かう私達。
しかし、醤油や味醂、ちょっぴりお酒のきいた、美味しい松前漬けも諦めきれません。
そんな私達の足元に現れたのは…。1枚のスルメイカ。
「でしょ」「拾っちゃう?」、目と目で通じ合う二人。
一歩一歩両親が近づいてきます。
サッと夫が車のミラーにスルメイカを乗せ、私は両親に話しかけて時間稼ぎ。
スルメイカに両親が気づきます。
「わー!イカだー」と素直な母に「もらっちゃおう」とちゃっかり者の父。
帰りの車内では、「あれなんだったんだろうね」「神様の贈り物ですかね」と私と夫の小芝居が始まります。
すると、「そうだね、神様。宝物だ」。マジか…。疑問を持たない両親に驚く私達。
「うん。それでいい。いや、それがいい」、またもや目と目で通じ合いました。
震災の津波を受けたあの市場は建て替えられましたが、両親の胸の中で、あのスルメは宝物のまま生きています。
本当のことを打ち明けたら、父は「1本取られた!」というかもしれません。
私は「10本だよ、イカだけにね」と返すつもりです。
そしてこの内緒の時間がずっと続くことと、年々老いていく両親と、あの松前漬けの話をする年末がこれから何度も繰り返すことを私も夫も願っています。
「おせちとわたし」 ノミネート作品24
「重箱の涙」
昨年、警察官を定年退職したが、三十年以上の昔、忘れられないおせち料理の話がある。
刑事だった私が年の瀬に逮捕したのは二十歳の被疑者Nだった。
粗暴犯で相手に大きな傷害を負わせた。Nは若いがすでに多くの前科前歴があり、取調室でも不敵な薄笑いを浮かべるだけで雑談には応じるが犯した罪は認めない。
この手の被疑者には根気よく付き合って自供の隙を狙うしかないのだが、Nの拘留期間は年を越すことが予想されていた。
明日が大晦日という日。私とNは朝から取調室で対峙していたがそのうちに昼休みになった。
現在では被疑者の昼食は必ず留置場に戻って摂る決まりだが、当時は取調室に官弁という粗食の弁当を持ち込んで摂らせていて、逃走防止の観点から取り調べる刑事と一緒に食べていた。
Nはプラスチックの箱に入った白米と佃煮、揚げ物が一個だけの弁当を黙って咀嚼する。
その前で私は共働きの妻が作った弁当を広げた。
そういえば、少し早いけどおせち料理を作ったからと、今日は小さな重箱だ。
Nは下を向いて箸を口に運んでいる。
少し迷って私はおせちの幾つかを重箱の蓋に載せてNに押しやった。
昆布巻き、蒲鉾、お煮染め、八幡巻き。
箸を止めたNは驚いて私を見た。
「数の子とか高いのはないで。我慢しろ。」
「え?いいんですか?」
「いいよ。口に合うか?」
頭を下げたNは全てを平らげたがやがて箸が震え、重箱の蓋に涙が伝った。
知っていた。Nは離婚した両親に見放されて施設で育った。
「いいですね…手作りのおせち。」といったNが両手を膝の上に置いて居住まいを正す。
これは自供するサインだ。
「N君も。手作りのおせち、作ってくれる好い人えを早くみつけや。」そしてNは罪を認めた。
三十年以上前の規則がない時代に私がしたことは今なら便宜供与で処分ものだ。
だが、あれは頑なだったNが重箱の蓋に落とした涙と一緒に、手作りのおせち料理の味が落とした取り調べだったのだと今でも信じている。
昨年、警察官を定年退職したが、三十年以上の昔、忘れられないおせち料理の話がある。
刑事だった私が年の瀬に逮捕したのは二十歳の被疑者Nだった。
粗暴犯で相手に大きな傷害を負わせた。Nは若いがすでに多くの前科前歴があり、取調室でも不敵な薄笑いを浮かべるだけで雑談には応じるが犯した罪は認めない。
この手の被疑者には根気よく付き合って自供の隙を狙うしかないのだが、Nの拘留期間は年を越すことが予想されていた。
明日が大晦日という日。私とNは朝から取調室で対峙していたがそのうちに昼休みになった。
現在では被疑者の昼食は必ず留置場に戻って摂る決まりだが、当時は取調室に官弁という粗食の弁当を持ち込んで摂らせていて、逃走防止の観点から取り調べる刑事と一緒に食べていた。
Nはプラスチックの箱に入った白米と佃煮、揚げ物が一個だけの弁当を黙って咀嚼する。
その前で私は共働きの妻が作った弁当を広げた。
そういえば、少し早いけどおせち料理を作ったからと、今日は小さな重箱だ。
Nは下を向いて箸を口に運んでいる。
少し迷って私はおせちの幾つかを重箱の蓋に載せてNに押しやった。
昆布巻き、蒲鉾、お煮染め、八幡巻き。
箸を止めたNは驚いて私を見た。
「数の子とか高いのはないで。我慢しろ。」
「え?いいんですか?」
「いいよ。口に合うか?」
頭を下げたNは全てを平らげたがやがて箸が震え、重箱の蓋に涙が伝った。
知っていた。Nは離婚した両親に見放されて施設で育った。
「いいですね…手作りのおせち。」といったNが両手を膝の上に置いて居住まいを正す。
これは自供するサインだ。
「N君も。手作りのおせち、作ってくれる好い人えを早くみつけや。」そしてNは罪を認めた。
三十年以上前の規則がない時代に私がしたことは今なら便宜供与で処分ものだ。
だが、あれは頑なだったNが重箱の蓋に落とした涙と一緒に、手作りのおせち料理の味が落とした取り調べだったのだと今でも信じている。
「おせちとわたし」 ノミネート作品25
「五人のおせち」
私は二十歳のときから祖父母の在宅介護を始めた。
毎年祖父母と両親と私の五人でおせちを手作りすることになった。
巨大5リットルサイズの大根でなますを作り、具沢山のうま煮、丹波の黒豆、もちつき機で魚沼産米の餅も作った。
祖父母が九十歳前後になるまで約十五年続けた。
祖母は左半身不随だったが右手だけで器用に里芋の皮を剥いだし父は末期癌になっても大量の買い出しと人参、ごぼう等うま煮の司令官だった。
母も脚が悪いのに一日三軒もスーパーに行ってより安く美味しい食材選びをした。
祖父はかなり高齢なのにじゃが芋をきっかり1cm角に切ってお吸い物担当をした。
私も病身だったがみんなでわいわい言いながら調理する仲間に加わりたくて味見の係と食材の下ごしらえ担当として参戦した。
お正月には母の妹家族がおせちを食べに来るので総勢十人ほどの食料は大量だ。
皆自分の抱える病気の愚痴など言う暇もなく忙しい。売っているおせちは味の調整はきかないが、家族で手作りするから五人でアイディアを出し合って意見を言い合ってお正月の我が家は特にリベラル。
その後、祖父母と父がなくなり今は母と質素なお正月を過ごしている。
五人でいたわり、ねぎらい、支え、励まし、助け、慰めあって暮らした歳月の心ぬくもる思い出は、今も孤独な私を勇気づけてくれる。
おせちを作っていたようで実は五人の絆を編み、縁の糸を縦に横に紡ぎ、我が家の味を受け継ぐと共に、こんなに近い所に産まれ育ち集まったこの五人の生きた証を互いの心に刻む大切な営みを継受したのだと今では思う。
もう二度と五人で力を合わせて作った力作の味は再現できないが、もしも私がお嫁に行ったら今度は夫やその親族の方々の味を教えていただいて逆に私の生家の味もお伝えしたい。
食べることは生きること。私だけの大切なマイエピソードを心に温めて、来たるべきお正月を今年も楽しみにしている。
私は二十歳のときから祖父母の在宅介護を始めた。
毎年祖父母と両親と私の五人でおせちを手作りすることになった。
巨大5リットルサイズの大根でなますを作り、具沢山のうま煮、丹波の黒豆、もちつき機で魚沼産米の餅も作った。
祖父母が九十歳前後になるまで約十五年続けた。
祖母は左半身不随だったが右手だけで器用に里芋の皮を剥いだし父は末期癌になっても大量の買い出しと人参、ごぼう等うま煮の司令官だった。
母も脚が悪いのに一日三軒もスーパーに行ってより安く美味しい食材選びをした。
祖父はかなり高齢なのにじゃが芋をきっかり1cm角に切ってお吸い物担当をした。
私も病身だったがみんなでわいわい言いながら調理する仲間に加わりたくて味見の係と食材の下ごしらえ担当として参戦した。
お正月には母の妹家族がおせちを食べに来るので総勢十人ほどの食料は大量だ。
皆自分の抱える病気の愚痴など言う暇もなく忙しい。売っているおせちは味の調整はきかないが、家族で手作りするから五人でアイディアを出し合って意見を言い合ってお正月の我が家は特にリベラル。
その後、祖父母と父がなくなり今は母と質素なお正月を過ごしている。
五人でいたわり、ねぎらい、支え、励まし、助け、慰めあって暮らした歳月の心ぬくもる思い出は、今も孤独な私を勇気づけてくれる。
おせちを作っていたようで実は五人の絆を編み、縁の糸を縦に横に紡ぎ、我が家の味を受け継ぐと共に、こんなに近い所に産まれ育ち集まったこの五人の生きた証を互いの心に刻む大切な営みを継受したのだと今では思う。
もう二度と五人で力を合わせて作った力作の味は再現できないが、もしも私がお嫁に行ったら今度は夫やその親族の方々の味を教えていただいて逆に私の生家の味もお伝えしたい。
食べることは生きること。私だけの大切なマイエピソードを心に温めて、来たるべきお正月を今年も楽しみにしている。



ハルメク
「おせちとわたし」思い出話コンテスト
あなたの「おせち」にまつわる、
楽しく笑って泣けるエピソード、
心温まるストーリー等を
200字〜800字程度でご投稿ください。
※お一人様一作品のみご応募可能
「おせちとわたし」思い出話コンテスト
あなたの「おせち」にまつわる、
楽しく笑って泣けるエピソード、
心温まるストーリー等を
200字〜800字程度でご投稿ください。
※お一人様一作品のみご応募可能
おせちにまつわるエピソード、ペンネーム、氏名、年齢、住所、電話番号、メールアドレスを下記ボタンよりご入力をお願いいたします。
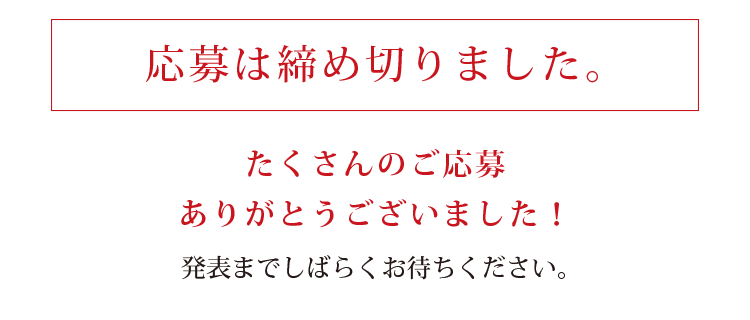
おせちにまつわるエピソード、ペンネーム、氏名、年齢、住所、電話番号を下記住所までお送りください。
※郵便でご応募の場合は8月26日(月)必着です。
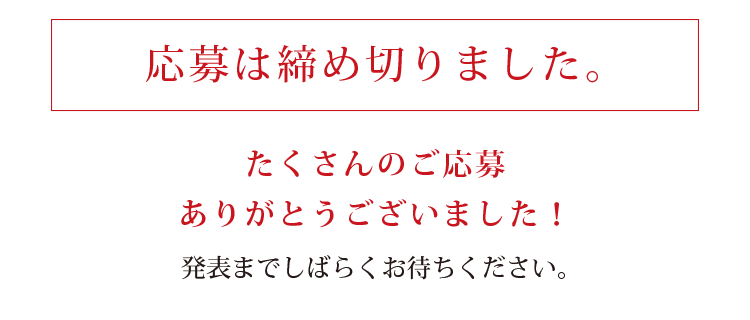
※郵便でご応募の場合は8月26日(月)必着です。
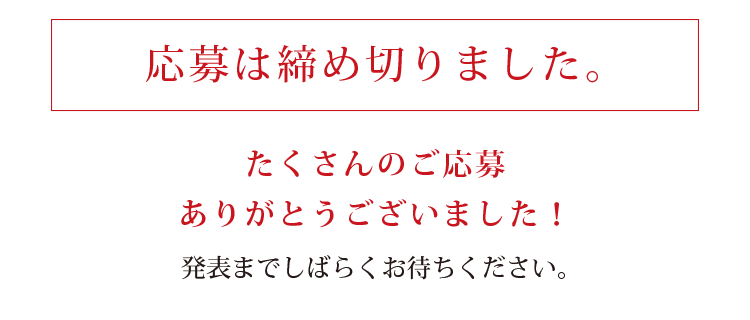
● 厳正な審査の上、受賞者を決定いたします。
● 受賞作品は「ハルメク365」および「ハルメクのおせち 特設サイト」等で10月上旬頃発表いたします。
● 受賞者には、発表後にメールまたは電話にてご連絡いたします。受賞されなかった方にはご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。
● 受賞作品は「ハルメク365」および「ハルメクのおせち 特設サイト」等で10月上旬頃発表いたします。
● 受賞者には、発表後にメールまたは電話にてご連絡いたします。受賞されなかった方にはご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。
審査委員長:
雑誌「ハルメク」編集長 山岡朝子
審査委員:
フリーアナウンサー/文筆家 住吉美紀氏
審査委員:
ハルメク 通販本部長 金山 博
雑誌「ハルメク」編集長 山岡朝子
審査委員:
フリーアナウンサー/文筆家 住吉美紀氏
審査委員:
ハルメク 通販本部長 金山 博
大賞:「ハルメクのおせち 福寿」(1人前、2人前、3人前、4人前、6人前からお好きなおせちを1台プレゼント)
感涙賞:「ハルメクのおせち 彩」2人前
笑えるde賞:「ハルメクのおせち 彩」2人前
※賞品は2024年12月28日または29日にお届けいたします。
感涙賞:「ハルメクのおせち 彩」2人前
笑えるde賞:「ハルメクのおせち 彩」2人前
※賞品は2024年12月28日または29日にお届けいたします。
■ 個人情報の取り扱い
応募者の個人情報は、当コンテストの運営および結果の通知のみに使用し、第三者に提供することはございません。
■ 注意事項
● 日本語での応募に限ります。
● 応募作品は未発表のものに限ります。
● 作品受領の通知は行いませんのでご了承ください。
● 応募作品は返却いたしませんのでご了承ください。
● 受賞作品は「ハルメク365」および「ハルメクのおせち 特設サイト」等で10月上旬頃発表いたします。
● 応募作品は未発表のものに限ります。
● 作品受領の通知は行いませんのでご了承ください。
● 応募作品は返却いたしませんのでご了承ください。
● 受賞作品は「ハルメク365」および「ハルメクのおせち 特設サイト」等で10月上旬頃発表いたします。
■ 作品の利用について
● 応募者は、応募作品について著作者人格権を行使しないものとします。
● 当社は、応募作品を当社のウェブサイト、出版物、その他あらゆるメディアにおいて利用することができるものとします。
● 当社は、応募作品を編集、改変、翻訳、改訂等の必要な変更を加えたうえで利用することができるものとします。
● 当社は、応募作品を当社のウェブサイト、出版物、その他あらゆるメディアにおいて利用することができるものとします。
● 当社は、応募作品を編集、改変、翻訳、改訂等の必要な変更を加えたうえで利用することができるものとします。

株式会社ハルメク
「おせちとわたし」思い出話コンテスト
事務局 (広報室内)
Email:pr@halmek.co.jp
「おせちとわたし」思い出話コンテスト
事務局 (広報室内)
Email:pr@halmek.co.jp
© Halmek Corporation All rights reserved.
おせちとわたし(おせわた)2025
おせちとわたし(おせわた)2025


